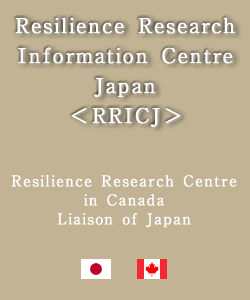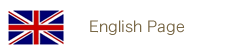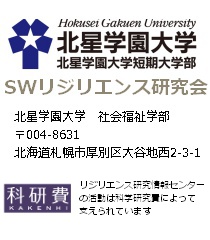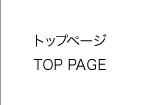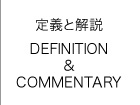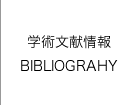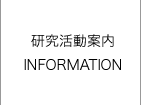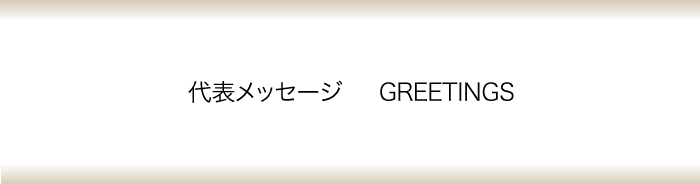ご挨拶
関東学院大学、人文科学研究所
SWリジリエンス研究会代表 秋山 薊二

リジリエンス研究情報センターのサイトにおいで頂き、心から御禮申し上げます。
2011年3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う原発事故、2016年の熊本地震、2014、2018年の西日本豪雨災害などを通して、被災からの復興、被災者と地域の支援、災害予防などが重要な研究テーマになりました。さらにこのテーマに関する研究・調査の学域も人文科学系、社会科学系、医学系、理工学系と多岐にわたります。この様な中、リジリエンス(resilience)と言う概念に注意が向けられる様になりました。リジリエンス研究は文献を遡れば、1950年代から始まっています。1990年代の研究により、児童発達、精神医学、心理学などの分野で研究が活性化し、現在に至っています。
リジリエンスを一言で表現すると、大きなリスクを伴う体験をしても不適応に陥らず、適応し成長して行く、もしくは以前と同じ状態を維持する、一群の人々を表す言葉です。そもそもは、物体にかかる負荷に抗して元の形状に戻ろうとする物理学の用語でしたが、人が逆境を克服する力や状態を指す言葉として、心理学、精神医学を中心に現在は使われています。物理学用語であったストレスが医学、心理学、社会福祉学で使われるようになったのと類似しています。このことは、リジリエンス研究の範域が広いことと、汎用性の高さが伺えます。
SWリジリエンス研究会は、ソーシャルワーク界の研究者、現場実践者の力を集結して、心理学、児童発達学の研究成果を踏まえ、リジリエンス研究を進展させようとの意図で出来上がりました。その一つの活動がSWリジリエンス研究情報センターによる情報発信と情報受信です。皆様方の協力をお願いするところです。
リジリエンスは現在、流行語のように各方面で使われ始めました。しかし、その概念理解にはズレが見られます。我々のもう一つの目標は、国際研究連携及び国内研究者・現場実践者の連携をはかり、ソーシャルワークの実践方法としてリジリエンスを確立させることです。それが児童福祉分野のみならず、広く国内に山積する社会福祉、社会保障の課題に取り組むべき方途であると考えますし、国難とも言える災害被害者への支援がより有効なものになると考えています。
リジリエンスを単なる「新しい用語」で終わらせることなく、概念研究と方法研究に裏打ちされた実践から生まれる知見をもとに、ソーシャルワークの効果を実証できるものに育てたいと願っています。
ソーシャルワーク実践者、ソーシャルワーク研究者の日毎の努力と研鑽は、新たにリジリエンス視点を導入することにより、新たな展望が開かれると信じています。
この様な理念のもと、SWリジリエンス研究情報センターを育てて行く所存で御座いますので、皆さまのご協力とご支援を宜しくお願い致します。