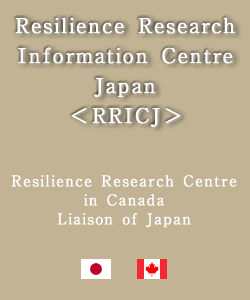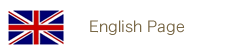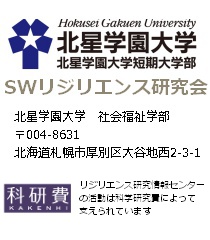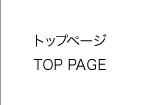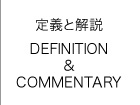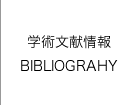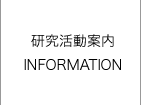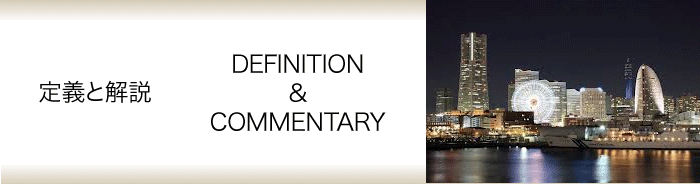リジリエンスの定義と解説
<解説> リジリエンスとは「逆境・困難・難事、トラウマ、悲劇、脅威もしくは強いストレスに遭遇した際、個人が明白な適応行動を顕わすに至る、力動的な過程」と一般的には概念化されている。リジリエンスはストレングスや発達上の強さ(assets)とは異なる。ストレングスは人が直面する逆境・難事(adversity)には関係なく、総ての人が持つなにがしかの特徴の一つである。逆境・難事・悲劇の下で、ストレングス(強さ)は、異なったものになる。一例として、2001年発生の9.11アメリカ同時多発テロ事件において、被害者救済に出動した勇気ある屈強な警察官、消防士の中から多数のPTSD患者が生まれたことは、よく知られている。彼らは強健かつ勇敢であり、責任感・義務感(ストレングス)は強いが、悲惨な状況に打ち克つ、精神的な意味でのリジリエンスはなかったと言える。両親に見守られ良い学校に通っていても、豊富な社会資源が提供され育まれているか否かが、リジリエンスに影響すると考えられている。優秀な成績、円満な家族、豊富な知識、高い運動能力は、それぞれ疑うことのない人の強さ(ストレングス)である。だが、adversityに遭遇しないと、それがリジリエンスになるかどうかは分からない。リジリエンスは二元構成になっている。第一構成がadversityの出現と遭遇、第二構成はそのadversity遭遇の結果として、明瞭な適応行動の表出である。この二元構成は二つの側面を意味する。即ち、第一は「明らかな適応」、第二が「重大な危険(adversity):時には状況であり、時には出来事」についてである。一つの視点から、adversityを定義すると「統計学的に適応を阻み、困難にする、好ましくない生活条件・状況に関するあらゆるリスク」と言う事が出来る。例えば、貧困、DV・虐待を起こしている家族、被虐待児、被DV者、家出した子ども、精神病患者を親に持つ子ども、災害・惨事の経験などがこれに該当する。一方、「明らかな適応とはライフ・ステージにおいて特別な課題・出来事に直面した時、社会的適性、社会的受容に基づいた行動が顕在すること」と考えることが出来る。上述のアメリカ同時多発テロの後に精神な苦痛や疾患が発生しないことなどを例として挙げることが出来る。Michael Ungarはこの標準的な定義には、他の社会システムに於いて人がどのようにリジリエンスを表すかの、文化及び背景脈絡の差異が十分に考慮されていない問題があると主張している。また、ストレングスの大御所であるSaleebey, D. (2013)はリジリエンスの概念上の問題点を指摘している。これに関しては別添の解説をこのPDFから参照下さい。![]()
以上を踏まえ、何人かの定義を紹介する。
- Michael Ungar (2011)の定義:
- 「リジリエンスとはその人にとって重い逆境、重大な困難・難事が表れる中で、個人の心理的、社会的、文化的、身体的、物的資源が本人に作用する方向を探し求め、安定した生活(ウエルビーング)を維持する能力であると共に、これらの資源が文化的に本人にとって意味ある方法で提供される様に、調整し利用する、個的・集合的な能力のことである。」
原文:“In the context of exposure to significant adversity, resilience is both the capacity of individuals to navigate their way to the psychological, social, cultural, and physical resources that sustain their well-being, and their capacity individually and collectively to negotiate for these resources to be provided in culturally meaningful ways.”
- 門永朋子(2011)/Mark Fraser(2004)
- 「逆境にもかかわらず、うまく適応すること」
以下、石井京子論文(2009)より
- Rutter (1985)
- 「深刻な危険性にもかかわらず、適応的な機能を維持しようとする現象」
- Masten, Best, & Carmezy (1990)
- 「困難で、脅威的な状況にもかかわらず得られる望ましい結果やその結果が得られる過程、あるいはその過程を支える許容力や結果」
- Garmezy (1991)
- 「再生に向けての足がかりに向けての跳ね返りの性癖や再生に向けての力」
- Werner (1993)
- 「逆境や障害に直面してもそれを糧としてコンピテンスを高め成長・成熟する能力や心理的特性」
- Grotberg (1995)
- 「生活上の困難や災害が引き起こす障害を予防して最小限とし克服するものであり、生命を強める普遍的な可能性」
- Luther, Cicchetti, & Becker (2000)
- 「逆境にあっても心理的あるいは社会的な不適応症状や問題行動に陥ることを是正し、前向きの適応をすることができる動的過程」
- Grotberg (2003)
- 「逆境に直面した時にそれを克服し、その経験によって強化される場合や、変容される人が持つ適応力である」
- 石毛・無藤(2005)、小塩・中谷・金子・長峰(2002)
- 「非常にストレスフルな出来事を経験したり、困難な状況になっても精神的健康や社会的適応行動を維持する、あるいは回復する心理特性」