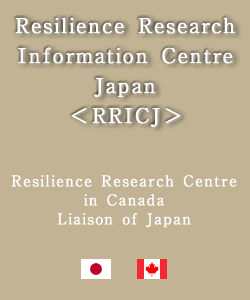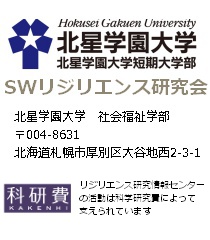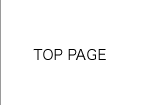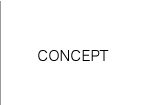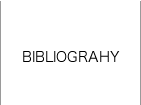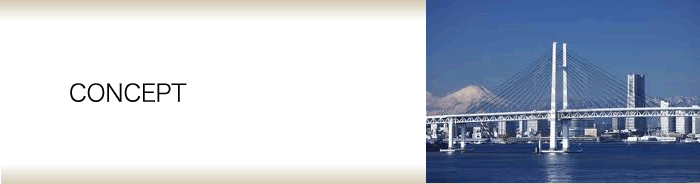リジリエンスは心理系、社会系、生態学、医学系、理工学系などの分野で用いられる学術用語です。
そもそもは物理学で用いられた、物質の衝撃や負荷を受けてもそれを跳ね返し、元に戻る性質を言い表す言葉でした。従って、この用語は学問分野によってそれぞれ特徴が表れるため、訳語に多少異なりがあります。回復力、復元力、弾力性、反発力、克服力、しなやかさ、強靱性、耐性、抗病力、最近では災害を念頭に置いた、災害復興力、防災力などを意味する言葉としても使われるようになり、多様です。
人間に対するリジリエンス研究は1970年代からありましたが、1990年代のMastenらの研究により、精神障害の親に育てられながらも社会的に自立適応を果たした子どもの研究により、リジリエンスは注目され、精神医学、心理学で導入されるようになりました。これを契機にソーシャルワークでは児童福祉研究の分野から研究が始まりました。日本のソーシャルワーク研究においても、子ども家庭福祉分野の研究者によってリジリエンス研究の先鞭がつけられました。
さて、リジリエンスの斬新性は、その言葉が新しいのではありません。人の営為の背景にある社会生態をパラダイムとして捉え、ソーシャルワーク実践として、リジリエンスを育む事を目指す新たなソーシャルワークの概念が芽生えて来ているところです。このリジリエンス概念は実証研究の積み重ねられて生まれた概念であることから、近年取りざたされているエビデンスに基づく実践にとも強い関連性が見られます。単純化して説明すると、困難の多い状況におかれながらも、問題なく社会に適応し、自立する一群の人々の発見からこの研究は始まっています。適応できず問題を抱える人と、適応を果たした人を比較する事により、何が作用して自立が可能になったかが、導き出されます。当初はリスク要因とプロテクティブ要因の有無が検証され、リスク要因を軽減し、プロテクティブ要因を増大すれば問題は予防できるとの考え方でした。しかし、二つの要因に相互作用があること、環境、制度、文化的な意味などが複雑に絡み合っていることが判明して来ました。更に、負の要因の多い状況のみならず、新たに起きる困難・難事(adversity)にどう立ち向かい、克服するかが新たな視点として生まれてきました。
同時に困難・難事もまた、社会、制度、地域、文化によって、異なることが分かって来ました。東京に15センチほどの積雪があれば、飛行機や電車は止まり、通勤・帰宅が出来ず、転んで怪我人が出たりで、ほぼパニック状態の難事発生ですが、札幌や秋田で15センチほどの雪が積もったからと、飛行機や電車が止まることはないでしょう。この二つを分けるのは何か、北国には積雪に対するプロテクティブ要因があり、問題なく人々は生活を営みます。これもリジリエンスです。困難・難事はその社会、環境、文化、地域の資源によって、当たり前の出来事になることもあります。
この様に子ども、家庭、地域、社会までを包摂する、新たな視点がリジリエンスです。換言すると、リジリエンスによるソーシャルワークによりミクロからマクロまでを捉える、新たなソーシャルワーク実践方法の萌芽が始まっていると言えます。リジリエンスの四つの鍵となる概念は、リスク要因、プロテクティブ要因、逆境・困難・難事(adversity)そして社会生態学です。
リジリエンスの概念を図示すると次の様になります。

図-1は子どもを中心としたリジリエンス研究の一般的概念です。劣悪な生活環境、家庭崩壊、被虐待、心理的ダメージなどを“逆境(adversity)”として捉え、ここからどのように社会適応させるかが課題でした。社会適応を促進する要因をプロテクティブ要因(Protective factor=保護要因、防御推進要因などと訳される)、それを阻害する要因をリスク要因として分類し、プロテクティブ要因の特定、形成過程、リスク要因との関係を探求し、プロテクティブ要因の形成・促進・導入を行い、個人の適応を目指す研究でした。当初は個人の特性(Factor, I am)に焦点が当てられていましたが、研究が進むとそればかりではなく、環境的要因(Factor, I have)、習得・獲得要因( Factor, I do or I can)なども関連していることが分かって来ました。不幸な境遇にある、子どもの適応自立を目指すリジリエンス研究が持つメカニズムを更に他の分野(高齢者福祉、地域福祉、福祉政策など)にも応用しようとする、動きが出てきました。これらは、高齢者のリジリエンス、地域のリジリエンス、社会のリジリエンスと呼ばれます。この様な時代の流れを考えると、ミクロからマクロの社会問題の解決や人々のウエルビーングを目指すソーシャルワークはその支援アプローチにリジリエンスを取り入れ、確立することが必要になって来ました。ここで問題となるのはadversityの捉え方です。これまでの研究では逆境(不幸な境遇、苦労の多い身の上)と捉えてきましたが、この概念を広げることが必要になります。例えば、メゾレベルの視点で見れば、児童養護施設で生活していることそれ自体が、ごく普通の児童とは異なった、adversity (恵まれた環境ではない、難事)である、と見なすことが出来ます。また、シャッター商店街や限界集落は地域住民の難事です。

図-2はリジリエンス概念を広げたものです。所与の環境、文化、制度、地域、仲間、資源、が社会生態を形成しており、そこで生活を営む人々が直面する難事や困難をadversityとして捉えると対象の一般化が可能になます。それはソーシャルワークの支援アプローチとして確立することを意味します。難事を克服した者と克服できなかった者を比較することにより、克服を可能にしたプロテクティブ要因を究明し、それを取り入れた支援・援助を行うこと、ここがリジリエンス・ソーシャルワークの鍵概念になると思われます。
ストレングスとの混同を避けるため附言しますと、ストレングスは誰もが多かれ少なかれ、それぞれの分野で持っていますが、リジリエンスは難事に直面し、それを克服した者が持っているものです。難事(多種多様なものがあります)が表れないとリジリエンスもまた表れません。順風の中で問題なく生活している人々にリジリエンスはありません。
日本は現在、震災・津波、原発事故からの復興と再生、即ち、子どもや家庭のみならず、社会の難事をどう克服するかが問われています。