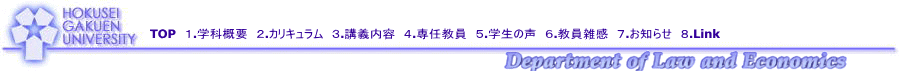
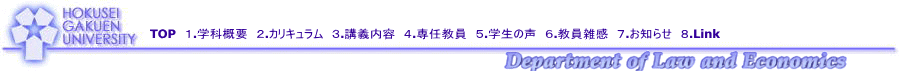

粗製濫造の感のある昨今の新書の世界。でも、埋もれさせてはいけない新書もあるはずです。そんな新書を岩本と齊藤が掘り起こして紹介することで、学生の皆さんを《買いたい》気にさせることはできないか。そう思い立って作ったページです。 新書は、現実の問題に真っ先に殴り込みをかける、いわば本の中の斬り込み隊長です。ですから、新書には、社会の現在の常識を《解体》する手がかりがきっとあります。一緒に新書を読みましょう。
|
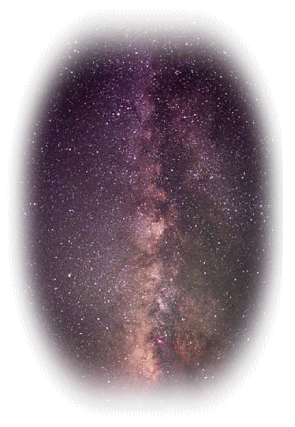 |
|
2003.5.21 井上史雄『日本語ウォッチング』(岩波新書540) 齊藤→岩本: 佐藤俊樹『不平等社会日本−さよなら総中流』(中公新書1537)は、序章の「『お嬢さま』を探せ!」と、後半の「『カリスマ美容師』のシステム」のところを立ち読みして、「購入決定」したと記憶しています。
待ち合わせ場所は、もちろん、本屋さんです。先日、ゼミのコンパがあり、集合場所が「ロビチカ」でした。少し早く着いたのですが、旭屋書店が移転し、東京堂書店も無くなってしまったので、時間をつぶすのに難儀しました。しかたないので、鞄から読みかけの新書を取りだして読んでいました。 なぜ、待ち合わせや時間つぶしに本屋を使うのか。両親がそうしていたこともあって、子どもの頃から、とくに疑問に思ったこともありませんでした。これも、佐藤『不平等社会日本』のいう、「目に見えない資産」でしょうか。 前回、岩本先生は、「学ぶ<楽しさ>と<苦しさ>」と書かれました。それを読んで、ふと思い出しました。 商品を安く売ることを「勉強する」と言うことがあります。一海知義『漢語の知識』(岩波ジュニア新書25)は、その一番最初の項目で、陶淵明の詩の一節、「時に及んでまさに勉励すべし、歳月は人を待たず」が、「若いうちにガリガリ勉強しろ」という意味ではないことを解説しています。学問と安売の共通部分、それは、「すこし無理をして○○する」ということのようです。ワクワク・ドキドキするときには、ますます、ちょっと無理をしてでもやってみようと思うでしょう。 佐藤『不平等社会日本』51頁以下の「データの落とし穴」は、読んでいても、ちょっと興奮するところです。「壁をうち破る」とでもいいましょうか。本書のサブタイトルである「さよなら総中流」を宣言して、従来の通説に斬り込むような感じです。 井上史雄『日本語ウォッチング』(岩波新書540)の帯紙には、「日本語は乱れてる!?」というキャッチコピーが刷り込まれていますが、著者は、「はじめに」のなかで、「現代日本語の変わりゆくさまを、さまざまな資料を使って、映し出してみる」としています。たとえば、最初に取りあげられる「ラ抜きことばの背景」では、「見れる」「食べれる」などの「ラ抜きことば」が、「平安時代から遠い将来にかけての長期的言語変化の中に位置づけられる」(同書29頁)ことが示されます。著者の調査と分析を追いかけていくと、なかなか興奮します。「『うざい』は『うざったい』に続いて、将来絶対はやると見た。待っているうちに、予測どおり都区内にも広がった」(同書93頁)。下降調で言う「……じゃないですか」については、「デスマス体の整備に貢献する表現である」(同書154頁)という説明がなされています。上で、「岩本先生は、〜書かれました」という(ラ)レル敬語を使いました。この(ラ)レル敬語も、「ラ抜きことば」の東京への普及に関係がありそうだとされます。そのほか、「じゃん」の進出や、北海道弁の「っしょ」の拡大などといったことも、長い歴史的な変化のプロセスのなかで、変化するしかるべき理由をもって生じていることが説明されるのです。同じ著者の『敬語はこわくない』(講談社現代新書1450)や『日本語は生き残れるか』(PHP新書167)が出たときには、自動的に買ってしまいました。 さて、いま私は(たぶん岩本先生も)興奮しています。さしたる疑問も感じずに読み流していた教科書的な記述が、実は「疑問まみれ」であることに気づかされたのです。そのことを指摘してくれたのは、経済法学科の学生でした。彼女がその気になって、少し頑張って文献を調べ、考察を文章にまとめたら、注目を浴びる論文が書けるかもしれません。それこそ、「勉強」の醍醐味かもしれないと思うのです。 |
|
2003.4.30 佐藤俊樹『不平等社会日本−さよなら総中流』(中公新書1537) 岩本→齊藤: 唐突ですが、齊藤先生は待ち合わせをするとき、どんな場所を使いますか。やはり本屋にかぎりますよね。
どうしてこんな話しをするかというと、以前、今回最初に紹介する著者の本を、1冊丸ごと待ち合わせのあいだに読んでしまって、そのお詫びをするためです。その本というのは、教育社会学者の竹内洋先生の『大学という病』(中央公論新社・2001年)です。とても面白くて、待ち合わせの時間がとうに過ぎているのも忘れて、読みふけってしまいました。竹内先生ごめんなさい。 竹内先生には、『学歴貴族の栄光と挫折』(中央公論新社・1999年)という著書があります(この本は<日本の近代>というシリーズのなかの1冊です。<日本の近代>はとてもよくできたシリーズで、日本の近現代史に興味がある方にはおすすめです。)。『学歴貴族の栄光と挫折』では、日本の近代化を指導したエリート層がどのように養成され、そのエリート養成コースが戦後どのようにして崩壊していったかが、興味深いエピソードともに語られています。戦前のエリートは、たんなる東京帝国大学卒業生ではありませんでした。正真正銘のエリートと認められるためには、第一高等学校や第三高等学校などの旧制高等学校(戦後、新制大学の教養部などに吸収されました。)を経た帝国大学卒業生でなければならなかったのです。私たちが通った新制の高等学校とは違って、旧制高等学校への進学率は、昭和になっても、20歳男子の100人に1人の割合を超えることがなかったそうです。まさにエリート中のエリートだったわけです。 ちなみに、私の大好きな哲学者の木田元先生は、戦後すぐに、農林専門学校から新制の東北大学の哲学科に進んだ<変わり種>の先生です。戦前のエリートから見れば、エリートの傍系も傍系です。そのため、第一高等学校から東北大学にきたある先生には、徹底して無視されたといいます。それほど、エリート意識が強かったということでしょうか。もちろん、木田先生もまたすごい方なので、けっしてそんなことに負けたりしませんが。詳しくは『闇屋になりそこねた哲学者』(晶文社・2003年)を読んでください。 さて本題。旧制高等学校は、多く見積もっても、20歳男子の100人に1人しか通らない超難関でした。その一方で、貧しい生活のなか、苦学してエリートの階段を上って身を立てた人の話も、美談としてよく語られました。しかし、竹内先生の実証研究によれば、それは幻想に過ぎなかったようです。第一高等学校にかぎってみると、なんと90パーセントが中産階級以上の裕福な家庭に育った子弟だったそうです。やはり戦前は、学問1つで身を立てることは難しかったのです。それが戦後一転しました。戦前は<カエルの子はカエル>にしかなれなかったわけですが、戦後は<トンビがタカを生む>ことも珍しくなくなりました。努力して勉強さえすれば、エリートとして出世するのも夢ではなくなったかにみえました。 しかし、戦後60年を迎えようとしている現在、すこし様子が違ってきました。社会学者の佐藤俊樹先生は『不平等社会日本−さよなら総中流』(中公新書1537)のなかで、「社会階層と社会移動全国調査」という調査データの分析から、次のような結論を導き出しました。<専門職または管理職のサラリーマンからなる「知識エリート」についていえば、「団塊の世代」(いまの学生の父親よりちょっと上の世代)あたりから、親の職業が子どもに「世襲」される割合が急に高まった。その結果、現在の日本は、「努力すればナントカなる」社会から「努力してもしかたがない」社会へ、そして「努力する気になれない」社会へと急激に変化しつつある。> 事態はもう少し深刻です。教育社会学者の苅谷剛彦先生は、子どもたちが、学ぶ意欲をもつ子どもと、学ぶ意欲を失った子どもに二極化されつつあると指摘します(「『中流崩壊』に手を貸す教育改革」「中央公論」編集部編『論争・中流崩壊』(中公新書ラクレ1))。そして、苅谷先生の分析では、母親の学歴が低いほど、学習意欲を失っている子どもが多くなっているとされます。つまり、親が高学歴の家庭に育った子どもは、学習意欲も関心もあって上級の学校に進むが、低学歴の家庭に育った子どもは、早い段階で学ぶことから降りてしまう。当然、そこには経済的要因もからんできます。はたして、それでいいのでしょうか。憲法26条は、すべての子どもたちに対して、学習する機会を<実質的に>保障するよう国に求めています。<学ぶ意欲がしぼんでしまった子どもたちの心に、学びの灯を再び灯すこと。> 憲法が求める<教育改革>とは、そのようなものでなければなりません(苅谷剛彦『教育改革の幻想』(ちくま新書329)を参照のこと)。そうでなければ、日本社会は、活力を失った<カエルの子はカエル>社会になってしまうでしょう。 北星学園大学も、4月に新入生を迎えました。おそらく、新入生のなかにも、さまざまな理由から、学習する意欲と関心を失いかけている学生がいるに違いありません。大学で学問を教える1人として、私もまた、身をもって学生たちに学ぶ<楽しさ>と<苦しさ>を伝えられればと思っています。中学校の先生で、素晴らしい国語教師だった大村はま先生は、こう言っています。「教師のもっともいい姿は、新鮮だということと謙虚だということですよ。」(大村はま・苅谷剛彦・苅谷夏子『教えることの復権』(ちくま新書399))。新学期も1ヶ月が過ぎようとしています。すこし姿勢を正して、教室に向かおうと思います。 1ヶ月以上のご無沙汰でした。そのため、勢いで長くなってしまいました。すみません。 |
 |
|
|
2003.3.17 佐々木知子『日本の司法文化』(文春新書089) 2003.3.8 秋山謙三『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書[新赤版]809) 2003.3.5 後藤昭『わたしたちと裁判』(岩波ジュニア新書288) 2003.2.28 川島武宜『日本人の法意識』(岩波新書[青版]630) 2003.2.25 江畑謙介『日本の軍事システム──自衛隊装備の問題点』(講談社現代新書1543) 2003.2.24 加藤尚武『戦争倫理学』(ちくま新書382) 2003.2.23 斎藤美奈子『戦下のレシピ──太平洋戦争下の食を知る』(岩波アクティブ新書37) |