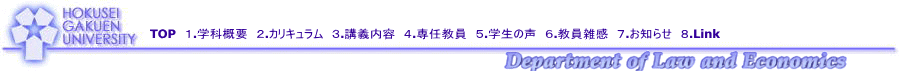
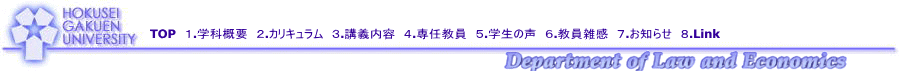

|
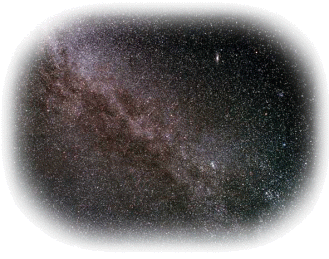 |
|
2003.3.17 佐々木知子『日本の司法文化』(文春新書089) 齊藤→岩本: 訃報といえば、同じく2月26日に、鉄道紀行作家の宮脇俊三氏が死去されました。宮脇氏は、中央公論社(現・中央公論新社)で、雑誌「中央公論」編集長、常務取締役などを務めた後、作家に転身されました。「世界の歴史」「日本の歴史」シリーズは、宮脇氏の仕事です。さらに、出版部長として中公新書の創刊に携わったのも宮脇氏です。宮脇氏の著作の多くは文庫化されており、鉄道紀行全集も出版されていますが、『時刻表一人旅』(講談社現代新書620)は唯一の新書版の著作でした。同書や、原田勝正『汽車・電車の社会史』(講談社現代新書713)など、とくに新書と意識することもなく読んでいました。最近は、櫻井寛『世界の鉄道旅行案内』(講談社現代新書1518)という楽しい本もあって、新書も多様化した感じがします。出張好きか単なる旅行好きか?(笑)東京在住の江川卓氏は、年に1度九州へキャンプ取材に行くだけで大騒ぎですが、札幌にいる我々の場合、東京での学会や研究会に出席するだけでも出張であり、旅行です。
さて、岩本先生御紹介の秋山謙三『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書[新赤版]809)は、「疑わしきは被告人の利益に」の実践の難しさに関連して、「検察官は、あえて起訴するわけであるから、ともかく形としてはそれなりの証拠を出してくる。被告人が否認していても、最初から『起訴されたのだから犯人ではないか』と疑ってかかる裁判官なら、それで満足し、それだけで有罪判決をするかもしれない。有罪率が九九・九パーセントという統計が、裁判官にある種の安心感を与えている、ということもあるだろう」と指摘しています。 これに対して、検察の側から、佐々木知子『日本の司法文化』(文春新書089)は、「検察は、証拠状況から『有罪の確信』が得られないと判断すれば、どれだけ残念であっても不起訴処分にする」といいます。有罪率99.9%についても、「起訴段階で裁判官の判断基準と同じレベルを課す結果、無罪率が極めて低いのは当然なのである」と主張します。「裁判所がろくに審理をしないから無罪が出ない、冤罪が生まれるのだといった批判をする人がいるが、それは違う。わが国の無罪率が極端に低いのは──それがいいかどうかの評価は別として──検察が起訴段階でのハードルをうんと高くし、慎重すぎるほどのスクリーニングをかけている結果なのである」というのです。日本は「超精密司法の国」であり、日本の法廷は「検察本命のレース」であると佐々木氏はいいます。「弁護側がアリバイ証拠をぶつけてきたとしても、そんなことで追いつかれたり追い抜かれたりなんていうことはまず起こらない」と。 「ロス疑惑」は、20年余。「まだ最高裁がある!」で有名な八海事件は、差戻しを重ねて第3次上告審判決まで17年余。八海事件について、上田誠吉=後藤昌次郎『誤まった裁判』(岩波新書[黄版]81)は、「事件が最高裁に係属するようになってから、広島高検の検事は吉岡の五人共犯説を維持するために熱心に吉岡のもとに足をはこんでいる」と指摘しています。「不幸なことにこれまで確かに──とくに戦後の一時期──少数ながらも冤罪はあった。それを刑事司法機関は反省し」たと佐々木氏は述べていますが、「わが検察はその伝統として、無罪が出るのを非常に嫌う」という体質があることも認めています。そして、「絞りに絞りをかけ、よほどのエリートしか刑務所に入れない仕組み」と佐々木氏の頌した日本の刑事司法が、既に佐々木氏も懸念を示していたように、その前提を喪失しつつあるのだとしたら・・・。 |
|
2003.3.8 秋山謙三『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書[新赤版]809) 岩本→齊藤: 藤原彰さんが、2月26日に逝去しました。15年戦争を体験として語れる世代の方がまた一人いなくなりました。ご冥福をお祈りいたします。
さて、齊藤先生の出張好き(正確には単なる旅行好き?)は知っていましたが、それが高じて、航空関係の本まで読み漁っていたとは。正直驚きました。私は、飛行機に乗ると、たびたび「航空性中耳炎」にかかってひどい目に遭いますので、できるかぎり陸上移動を心がけています(私は江川卓か?)。日常の交通手段は、もっぱらバスと地下鉄です。札幌の地下鉄も、さすがに午前8時台には瞬間風速的に混雑します。そのとき困ることは、夏場は目のやり場、一年通じて手のやり場ですね。妙な手の動きが痴漢と間違われたら・・・。というわけで、今日は「痴漢冤罪」について考えてみたいと思います。 読売新聞社社会部『ドキュメント裁判官−人が人をどう裁くのか』(中公新書1677)によれば、2001年、東京都の電車内で起きた痴漢事件(東京都迷惑防止条例違反〔卑猥な行為〕または強制猥褻容疑での検挙)は2057件で、その3年前に比べて400件も増えているそうです。その一方で、痴漢とされた男性が裁判で無罪となったケースも、2000年以降、10件を超えるといわれます。身に覚えのない痴漢容疑でも、その疑いを雪ぐために正式裁判に訴えるよりも(否認事件のため身柄を拘束されると、仕事にも行けない)、略式命令で5万円の罰金を払う方を選ぶ人も多いと思います。そうすると、潜在的な「冤罪」はもっと多いのかもしれません。 『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書[新赤版]809)の著者である秋山謙三さんは、20年以上の裁判官のキャリアをもつ弁護士さんです。彼は痴漢冤罪事件の恐ろしさを次のように述べています。「殺人事件などの重大犯罪ではないところに、逆にこの冤罪の恐ろしさがあり、それは一般市民にとっては、誰でも、いつ自分の身に降りかかってくるかもしれない性質の事件であって、決して他人事ではないというところにある・・・。」痴漢事件が起こる客観的状況は、もともと冤罪を生みやすいとされます。−混雑した電車のなかで、不特定多数のなかから痴漢を特定するのはきわめて難しい。さらに、被害者が特定の人をいったん名指しすると、その人を犯人だと思い込もうとする心理が働く。−このような状況で、被害者の供述証拠のみで、被告人を有罪とすることはきわめて危険です。冤罪を生まないためには、裁判官は、供述証拠を補強する物的・科学的証拠を検察に求め、それがないときには、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則に立ち返って、被告人を無罪にすべきである、と秋山さんは訴えます。 新書の世界では、「冤罪もの」が一つのジャンルとして確立されているといっていいでしょう。古くは、弁護士の後藤昌次郎さんの2冊の本があります。上田誠吉=後藤昌次郎『誤まった裁判』(岩波新書[青版]57)と後藤昌次郎『冤罪』(岩波新書[黄版]81)です(残念ながらいずれも入手困難)。新しいところでは、刑事訴訟法学者の小田中聰樹さんの『冤罪はこうして作られる』(講談社現代新書1145)があります。それだけ、日本の司法において冤罪が深刻な問題だということの表れなのでしょう。最近では、「ロス疑惑」と騒がれた三浦和義さんのケースは、マスコミと検察が作り上げた冤罪事件といってよいでしょう。「ロス疑惑」などといっても、いまの学生にはちんぷんかんぷんでしょう。それもそのはずです。三浦さんは、最高裁で無罪を勝ち取るために、20年4ヶ月という長い歳月を費やしたのですから。 秋山さんは問いかけます。なぜ日本の裁判官は、率直に「合理的な疑いを超える程度の証明がない」として無罪判決を書けないのかと。そして、「疑わしきは被告人の利益に」を実践できないことが、冤罪の最大の原因であると言います。元裁判官だけに、その言葉は重い。 |
|
2003.3.5 後藤昭『わたしたちと裁判』(岩波ジュニア新書288) 齊藤→岩本: 先週は出張でした。1日違いで、管制システムのトラブルに遭わずにすみました。ちょうど、園山耕司『航空管制の科学』(講談社ブルーバックスB-1399)を読んだところでしたので、トラブルの顛末についての報道もよく分かりました(ブルーバックスには、岡地司朗編『ジャンボ・ジェットを操縦する』(B-1276)もあり、木村拓也主演のドラマ「GOOD LUCK!!」(TBS-HBC)を楽しむためにも重要です)。飛行機モノでは、前間孝則『最後の国産旅客機YS-11の悲劇』(講談社+α新書15-1C)が、NHK「プロジェクトX」の「翼はよみがえった」では語られなかった、YS-11プロジェクトの全容と問題を描き出していて、テレビ番組とは異なる、書籍ならではのものがあります。「空気より重い航空手段」である飛行機が交通機関として今日の地位を確立する以前、豪華で快適な空の旅を提供した「空気より軽い航空手段」である飛行船。関根伸一郎『飛行船の時代 ツェッペリンのドイツ』(丸善ライブラリー078)は、ツェッペリン飛行船の誕生からヒンデンブルク号の炎上事故までの経過に関心があって読んだのですが、20世紀前半の社会に飛行船がどのように受け容れられたかが描かれていて、おもしろい読み物でした。
さて、藤原彰氏には、書名もズバリ、『餓死した英霊』もありますよね(こちらは読みましたが、岩本先生が紹介された『中国戦線従軍記』は未読でした。このコーナー、学生よりも自分の購入する本が増える墓穴企画のような気も・・・)。同書では、旧日本軍が捕虜となることを禁じていた問題についても論じられていますが、山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』(文春新書214)の「捕虜となった日本兵は、米軍の尋問に協力的だった」という指摘と併せて読むと、考えさせられるものがあります。従軍体験としては、山内久『私も戦争に行った』(岩波ジュニア新書351)もありました(現在は品切)。南方戦線での飢餓状況も悲惨ですが、中国大陸での「兵隊生活」も重いものがあります。 川島武宜『日本人の法意識』を読んだのは、大学の教養部の頃だったでしょうか。対抗して(?)、中川剛『日本人の法感覚』(講談社現代新書950)を取りあげようかと思いましたが、品切れでした(もちろん、図書館で読めますが)。そこで、日本人の法観念の問題としても論じられる、いわゆる隣人訴訟を取りあげた新書がないかと思いました。近所の家に預けてあった子どもが溜め池に落ちて水死したことについて、亡くなった子の親が、預かった夫婦を訴えたという、あの事件です。授業などでも、しばしば話題にしていました。考えついたのは後藤昭『わたしたちと裁判』でした。学生の皆さんにはしばしば奨めているのですが、この本は、法律学の勉強を始める前に一読しておくとよいのではないでしょうか。1997年の刊行で、情報が古くなっている点もありますが、法律学を学ぶための頭の準備をするのに好適な1冊だろうと思います。中学生・高校生向けとうたわれているジュニア新書を大学生に奨めるのは失礼かもしれませんが、1年生の皆さんは昨日まで高校生だった、ということで勘弁してもらいましょう。でも、一流の研究者がその能力を総動員して考え抜いた説明を展開してくれるジュニア新書は、場合によっては、とても贅沢な1冊なのかもしれません。本書も、裁判における法律の解釈・適用のしくみについて、具体例を挙げながら噛み砕いた説明がなされています。 新書で隣人訴訟に言及するものは他にもありましたが、今後のために温存することにします。 |
|
2003.2.28 川島武宜『日本人の法意識』(岩波新書[青版]630) 岩本→齊藤: 「食料がなくなることが戦争だ。」しかし、もっと恐ろしいのは、「食料がなくても兵隊は戦争できる」という旧日本軍の無茶な戦い方です。15年戦争では、日本の兵隊の多くは、敵の弾を受けて死んだのではなく、前線に食料や医薬品が届かなくて「餓死」したのです。歴史家・藤原彰さんは、自身の従軍体験を綴った『中国戦線従軍記』なかで、その事実を軍隊の内側から静かに告発します。
さて、江畑さんが言うように、自衛隊の装備は「国民の財産」です(私から見ると、それはいつか「償却」しなければならない「不良債権」にほかなりませんが)。しかし、自衛隊の装備は本当に「国民の財産」といえるでしょうか。タリバン崩壊後、アフガニスタンの復興が進むなか、日本政府は、アメリカからのたび重なる強い要請に応えて、イージス艦をインド洋に派遣しました。イージス艦は実は「アメリカの財産」ではないのか、と疑いたくなります(その疑いは濃厚)。イージス艦派遣をめぐる日本政府・自衛隊背広組・制服組・アメリカ政府の四つ巴の暗闘については、久江雅彦『9・11と日本外交』(講談社現代新書1622)が詳しくレポートしています。 「自分の財産と他人の財産」の区別が定かでないような、希薄な権利意識は、アメリカではなくて、日本の専売特許のはずなのですが・・・。そこで名著の誉れ高い川島武宜先生の『日本人の法意識』(岩波新書[青版]630)です(岩波書店のホームページでは「残部僅少」となっていますが、北星の生協には平積みです。皆さん生協にGo!)。川島先生は、さまざまな具体例を引いて、所有物が所有者の手の届かないところに置かれると、とたんに所有権がなんとなく弱くなったように感じる、日本人に特有の「所有権」意識を指摘します(皆さん、落とし物はちゃんと警察に届けていますか?)。このような意識は、所有権の絶対性を重んじる近代社会から見れば、遅れたものとされるのです(アメリカは海の向こうから他国の「財産」にあれこれ言うのですから、やはり日本人の「所有権」意識とは違いますね。)。 しかし、権利意識の高い社会は、ほんとに進んだ社会なのでしょうか。長谷川俊明『訴訟社会アメリカ』(中公新書891)が描き出したように、「事件屋弁護士」が死亡広告記事片手に訴訟の種(飯の種)を探してかけずり回っている「訴訟社会」が、まっとうな社会であるかは疑問です。多くの西欧語がそうであるように、権利(right)という言葉は、正しさを意味する言葉とイコールです。権利とは、「正当な取り分」に対する要求であることを忘れてはなりません。 |
|
2003.2.25 江畑謙介『日本の軍事システム──自衛隊装備の問題点』(講談社現代新書1543) 齊藤→岩本: 一昨日、斎藤美奈子『文壇アイドル論』を読み始めました。新刊のときに買いそびれていたのを、先日の研究会の折に北大生協で入手しました。
さて、私は「宇宙戦艦ヤマト」の世代ですが、ヤマトはカッコいいと思っても、映画「さらば宇宙戦艦ヤマト」のラストシーンの体当たりと、吉田満『戦艦大和ノ最期』(最初に読んだのは、お下がりの『少年少女世界のノンフィクション(3) 戦艦大和のさいご/真珠湾上空6時間』(偕成社)でした)に描かれた沖縄特攻作戦とは違う。そこには、「おかあさーん! 」と叫びながら重油の海に沈んでいった少年兵がいましたし、臼淵大尉の言葉は、古代進(「宇宙戦艦ヤマト」の主人公)の演説とは少し違う気がします。海戦もさることながら、荒木進『ビルマ敗戦行記』(岩波新書[黄版]198)などの陸戦の世界も悲惨です。 先日の斎藤美奈子『戦下のレシピ』は、その書名について、「戦争の影響で食料がなくなるのではない。食料がなくなることが戦争なのだ。その意味で、先の戦争下における人々の暮らしは『銃後』でも『戦時』でもなく『戦』そのものだった。だから『戦時下』ではなく『戦下』のレシピなのである。」といいます。そして、「あとがき」のなかで、「当時の暮らしから、耐えること、我慢することの尊さを学ぶという姿勢は違うような気がします。こんな生活が来る日も来る日も来る日も来る日も続くのは絶対に嫌だ! そうならないために政治や国家とどう向き合うかを、私たちは考えるべきなのです。」といいます。 ところで、江畑謙介氏は、「軍備はないに越したことはないのは事実だが、それを実現するのは不可能であろう。/軍備はできるだけ少ないに越したことはない。軍備はほぼ完全に非生産的なものだからである。」といいます。そして、「防衛装備を感情的に忌避するのは容易でも、〈中略〉これらの自衛隊の装備はわれわれ国民の税金で購入している、われわれの財産である。それがどんなもので、どのように買われ、使われているのかに、日本国民はもっと関心を持ってしかるべきだろう。」とします。「使わないために軍備は存在する」(江畑謙介『日本の安全保障』(講談社現代新書1375))という考え方に賛同するかどうかは別としても、軍事について一定の知識をもつ必要はあるのではないでしょうか。 |
|
2003.2.24 加藤尚武『戦争倫理学』(ちくま新書382) 岩本→齊藤: 研究室が同じ階の隣の隣の隣の・・・以下略・・・隣の齊藤先生ですが、いちおう慣例にしたがい、「拝復」。
斎藤美奈子さん(齊藤・岩本共通のアイドル!?)は問います。「なぜ戦争は食糧難を招くのか? 」。しかし、「明日食べるものがない平和を捨てて、明日の食べ物のある戦争を選ぶ人々」がいるのも確かです。事態はまったく逆さまですが、これもまた現実です。(「逆さま」といえば、「さかさまじん」というナンセンス絵本が思い出されます。笑えます。研究に疲れたときに、「目薬」代わりに読んでみてください。) だから、最近の平和学者はこう主張します。−世界が本当に平和になるためには、単に戦争がないという「消極的平和」が保たれているだけでなく、人々の幸福や福祉や繁栄が保障された「積極的平和」が追求される必要がある。開発国に生活する人々を思えば、この主張に大いに説得力があります。 しかし、戦争がないこと、そのこと自体に何か価値はないのでしょうか。保守の論陣を張る人たちはこう言います。−日本人は「平和ぼけ」している。「ただ生きること」にあくせくして、「善く生きること」を忘れている。命をなげうっても守るべきもの(「お国」)があることを忘れている。このような保守の論法にからめ取られないためにも、日本の文脈では、平和のなかで命をまっとうすること、それ自体に価値があるとあえて論じる必要があります。倫理学者の加藤尚武さんは、「『戦争の不在』が消極的であるという前提は間違いである」と批判します。「無事に生きる、平和に生きることそれ自体に、限りなく深い意味がある。それを支えるためには、外交、経済、国防、治安など、生活環境をささえる努力が必要である。その努力自体が、個人の生き甲斐となりうる。」生きるという究極の目的のために力を尽くすことが、私たちの生をいっそう充実したものとする。生きるという目的と生きるための手段が完全に一致している境地こそが、人間にとって「最高の幸福」であると、加藤尚武さんは言うのです。 対イラク戦争が現実味を帯びてきているなか、世界中の多くの人々が共有する、このような倫理的な直感が、戦争を止める最後のよりどころになると、私は信じています。「マジレス」してしまいました。それではまた。 |
|
2003.2.23 斎藤美奈子『戦下のレシピ−−太平洋戦争下の食を知る』(岩波アクティブ新書37) 齊藤→岩本: 「読書する人は少数民族である」(斎藤美奈子『趣味は読書。』)ならば、民族のホコリをまき散らしてやりましょう、などという企ては、しばしば酒の席で打ち上げられるのですが、この企画はアルコール燃料が尽きてからもなぜか飛び続けているのであります。
なぜ戦争は食糧難を招くのか? なぜ日本は米不足に陥ったのか? なぜ戦争末期に至って代用マヨネーズが登場したのか? 料理の不得手な私は、「読めて使えるガイドブック初登場!」という腰帯の宣伝文句に反して、著者があくまで「理由」を追いかけるところに惹かれました。 ですから、この本の「はしがき」の、「戦争中の食について、断片的に知っている人は少なくないだろう。米がなかったとか、いもの葉っぱまで食べた食べたとか、すいとんばかり食べていたとかだ。しかし、どんな状況で、なぜいもの葉っぱまで食べたのかまで想像するのはむずかしい。そこでこの本の上段では、戦争で人々の食生活がどう変わっていったかをたどることにした。」というくだりは分かるのですが、「はしがき」の最後が、「いつもあなたが読んでいる料理雑誌やグルメガイドのようなつもりで読んでもらえたらと思う。そして、もし興味を持ったら、実際に作って食べてみてほしい。文字に書かれた情報だけではわからないことが、きっと発見できるだろう。」と結ばれていることをどう読むか。やはり、自分で作らないと分からないのでしょうか。 |
 |
「買いたい」した新書一覧〈岩波新書〉秋山謙三『裁判官はなぜ誤るのか』 荒木進『ビルマ敗戦行記』 井上史雄『日本語ウォッチング』 上田誠吉=後藤昌次郎『誤まった裁判』 川島武宜『日本人の法意識』 後藤昌次郎『冤罪』 〈岩波ジュニア新書〉 一海知義『漢語の知識』 後藤昭『わたしたちと裁判』 山内久『私も戦争に行った』 〈岩波アクティブ新書〉 斎藤美奈子『戦下のレシピ』 〈講談社現代新書〉 井上史雄『敬語はこわくない』 江畑謙介『日本の軍事システム』 江畑謙介『日本の安全保障』 小田中聰樹『冤罪はこうして作られる』 櫻井寛『世界の鉄道旅行案内』 中川剛『日本人の法感覚』 原田勝正『汽車・電車の社会史』 久江雅彦『9・11と日本外交』 宮脇俊三『時刻表一人旅』 〈講談社ブルーバックス〉 園山耕司『航空管制の科学』 岡地司朗編『ジャンボ・ジェットを操縦する』 〈講談社+α新書〉 前間孝則『最後の国産旅客機YS-11の悲劇』 〈ちくま新書〉 大村はま・苅谷剛彦・苅谷夏子『教えることの復権』 加藤尚武『戦争倫理学』 苅谷剛彦『教育改革の幻想』 〈中公新書〉 佐藤俊樹『不平等社会日本−さよなら総中流』 長谷川俊明『訴訟社会アメリカ』 読売新聞社社会部『ドキュメント裁判官』 〈中公新書ラクレ〉 「中央公論」編集部編『論争・中流崩壊』 〈PHP新書〉 井上史雄『日本語は生き残れるか』 〈文春新書〉 佐々木知子『日本の司法文化』 山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』 〈丸善ライブラリー〉 関根伸一郎『飛行船の時代』 |