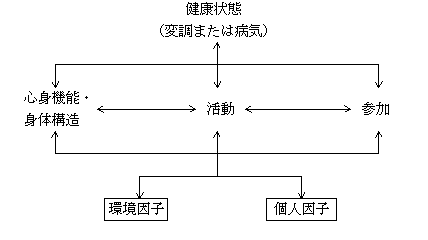障害とは
障害とは何かについて,厳密に定義することはかなり難しい問題である。
とりあえず,
障害の定義=心身の構造的あるいは機能的欠損あるいは不全(≒1980年機能障害)
障害に次のような性質があることにはまず異論がない。
-
・原因を問わない。病気,外傷その他いずれの原因でも,現に障害の状態にあれば障害として認定する。
・症状が固定若しくは永続すること。
比較的短期間に障害の状態が消失する見込みがある場合,通常は障害に区分しない。
・工学的な対応が難しいこと
・障害は認識の問題であり,社会の対応の問題であること。
障害の定義
『障害者基本法』(1993年11月に題名改正)第2条では,〔『障害者』とは,身体障害,精神薄弱又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。〕と定義された。ここでは,身体障害,精神薄弱または精神障害を総称したものを『障害』と呼称する一方で,同法の成立に際して決議された付帯決議で,『てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるもの』も障害者の範囲に含まれる,とされた。
障害の分類 ──────────────────────────── 身体障害 ①視覚障害 ②聴覚障害 ③平衡機能障害 ④音声・言語障害 ⑤そしゃく機能障害 ⑥肢体不自由 ⑦内部障害(心臓,腎臓等の内臓疾患,エイズ) ──────────────────────────── 知的障害 原因が18歳までにある。18歳以降の原因(痴呆)は除く。 ──────────────────────────── 精神障害 精神分裂病,躁うつ病等 ────────────────────────────
1)身体障害者:身体障害者福祉法で「身体上の障害がある18歳以上の者で都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」となっている。身体障害の内容は,「視覚障害,聴覚障害,肢体不自由」の3つに加えて,平成10年(1998)には心臓や腎臓などの内臓器官の疾患に加えて,「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」(エイズ)も含めて「内部障害」と称するようになった。この4つが主なものであるが,他に,発声困難や失語症などを含めた「音声・言語障害」,身体のバランスを保てない「平衡機能障害」,飲食物の飲み込みが困難な「そしゃく機能障害」などがある。
2)知的障害者:(従来,「精神薄弱者」といわれていたが,1999年に改称)とは,「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れて,日常生活に支障が生じているため,何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されている。この「知的障害」の判定基準は,「標準化された知能検査で知能指数が概ね70以下のもの」とされ「日常生活の支障」は,自立機能,運動機能,意志交換,探索操作,職業,生活文化など日常生活能力の到達水準を,総合的に同年齢の到達水準と比較して判定されることになっている。具体的には,計算ができない,漢字の読み書きが難しい,抽象的な思考ができない,などの特徴がある。
知的障害者には「療育手帳」が交付されるが,全国一律の基準は設けられていない
3)精神障害者:精神保健福祉法(1995)で「精神分裂病,中毒性精神病,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有するもの」と定義している。しかし,この定義は精神医療の分野で使用されるものであって,福祉の領域では「知的障害者を除く」と規定されている。そして精神障害者の70%以上は精神分裂病で占められている。
『障害者の権利宣言』の第1項
『障害者』という言葉は,先天的か否かに拘らず,身体的能力又は精神的能力の不足のために,通常の個人生活又は社会生活に必要とされることを,一人ではその全部又は一部,満たすことのできない人を意味する。
さらにWHO(世界保健機構)で,『障害』の概念を,疾患(外傷も含む)に起因して生ずる第1次障害のインペアメント,その帰結としての第2次障害のディスアビリティおよび第3次障害としてのハンディキャップというように,3つの次元に分けている。国際障害分類(ICIDH = International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps)と言われる。
インペアメント(impairment=機能障害)は,疾病の結果もたらされる身体面の器質的損傷または機能的不全で,医療の対象である。ディスアビリティ(disability=能力障害)は,主としてインペアメントに基づいてもたらされた日常生活や学習上の種々の困難であって,特殊教育諸学校における養護・訓練によって,改善・克服が期待されるものである。ハンディキャップ(handycap=社会的不利)は,インペアメントやディスアビリティによって,一般の人々との間に生ずる社会生活上の不利益,福祉や教育の対象である。
障害の分類と内容(永渕,2000より引用) ────────────────────────── 1.impairment:機能障害(心身の形態・機能の損傷) ────────────────────────── 視覚障害 内部障害 聴覚・言語障害 知的障害 肢体不自由 精神障害 ────────────────────────── 2.disability:能力低下(行動の欠如・制限) ────────────────────────── 行動能力の低下 器用さの能力低下 意志疎通能力の低下 状況判断能力の低下 移動能力の低下 特殊技能の低下 ────────────────────────── 3.handicap:社会的不利(社会・家庭での行為の制限) ────────────────────────── 家庭での生活困難 職業的自立の不利 通学・通勤上の不利 経済的自立の不利 作業上の社会的不利 社会参加の不利 ────────────────────────── 障害とその対処(永渕,2000より引用) ───────────────────────────────── 対 象 対処の基本 対処の主な内容 ───────────────────────────────── 機能障害 医療 1機能障害の改善(損傷の治療, impairment 治療的 手術による機能回復など) 2後遺症や合併症の予防・治療 ───────────────────────────────── 能力低下 リハビリ 1残存機能の強化(四肢の筋力増強) disability 代償的 2日常生活動作(ADL)の訓練 3補助具の使用(義肢の装着) ───────────────────────────────── 社会的不利 福祉 1家屋の改造(便所や階段の手すり) handicap 環境改善 2教育の機会の確保(児童の通学) 3職業的自立の援助(職業訓練) 4経済的自立の保障(手当,年金) ─────────────────────────────────
WHOはその改正案を検討の結果,2001年5月に決定した。これが国際生活機能分類(ICF= International Classification of Functioning, Disability and Health )である(新国際障害分類と言われることもある)。
第一に環境を含む背景因子が重視され,人間-環境相互作用モデルとなっている。第二に,能力障害を「活動」,社会的不利を「参加」とし,また病気だけでなく加齢も含めて「健康状態」とするなど中立的な表現で,より普遍的なモデルになっている
1980年版では,「障害」にのみ着目した内容となっているのに対し, 1999年版改正案では,生活の中での人間がもつ種々の機能と,その機能を果たすに際しての問題となりうる障害についてまとめた内容となっている。
諸概念の関連について,疾病による心身の変調から障害が発生し,その障害はまず「機能障害」が起こり,そこから「能力障害」,「社会的不利」へとつながっていくという関連になっているのが1980年版である。
改正案では, 1980年版の疾病によって生じる「障害」という表現を「健康状態」という表現で示している。その「健康状態」を「心身機能・身体構造」,「活動」,「参加」という3次元で表し,それぞれが相互に作用しており,また環境因子や個人因子といった背景因子を重視している。
こうした背景の特徴として,医学モデルから人間-環境相互作用モデルへの改正,3つの次元(心身,個人,社会)に区分することの変更はないが,環境を含む背景因子の重視,各因子の相互作用,相互関連,中立的・肯定的理解,表現があげられる。これには,ノーマライゼーションの概念,障害者の権利宣言,障害者の機会均等化に関する標準規則の採択等の障害者観の時代的変化が反映されている。
以上をまとめた以下のような図が発表されている。