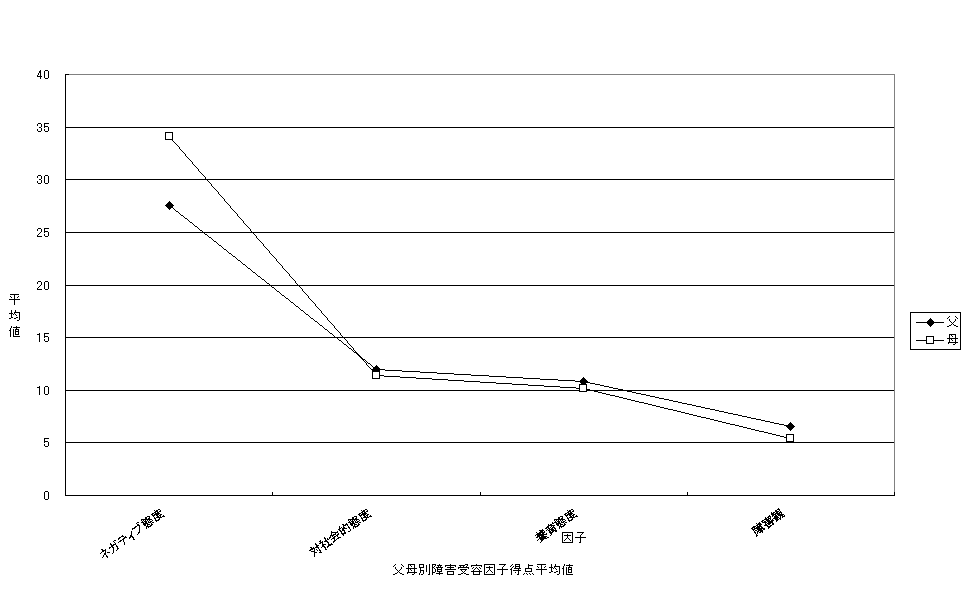障害児を持つ親の我が子の障害に対する態度についての考察
9907070
鷲見 彩
【目的】
生まれてきた我が子に障害や何らかの遅れ・発達上の問題があると知った時,家族はどのように受け止めていくのだろうか。障害,または発達上の問題がある可能性がある子どもをもつ親は,子どもの障害を受け入れることから始まり,子どもの成長に従って療育や就学,将来のことなど,障害をもたない子どもの親に比べ,悩みが多岐にわたり,深刻化する場合が多い。様々な問題を乗り越えるために,夫婦,および家族の一致した養育観と協力が必要だと考えられる。また,親は子どものニーズをとおして多くの専門家と関わる。信頼をおける専門家との出会いは親子共に重要なポイントとなり,子どもの問題を受け入れ,前向きに育てていこうとする親の重要なサポート者となるのではないだろうか。
以上をふまえて,本研究では親の「障害受容」に焦点を置き,父母間で子どもに対する認識(障害受容)に差がある(仮説①),関わった専門家に対する評価が高いほど障害受容得点が高い(仮説③),また,障害受容にコーピングのタイプが影響するのではないかとの立場に立ち,コーピングと障害受容の関連の有無(仮説④)についても検討する。さらに,子どもと関わる上で親にとって重要な存在となる専門家について,告知をした専門家と告知以降に関わった専門家に対する評価を比較し,告知をした専門家の方が,告知以降に関わった専門家よりも評価が低い(仮説②)のではないかという点と同時に,親が専門家に望む態度についても考察する。
【方法】
<対象>療育施設に通う就学前の心身障害幼児の親で,父25名,母47名,計72名(そのうち夫婦25組)。
<調査手続き>療育施設で調査用紙を配布し,持ち帰ってもらい,後日任意で提出させた。配布・回収期間は2002年10月5日から11月7日。回収率は37.9%であった。
<調査内容>①フェイスシート:回答者および子どもについて,②発達上の問題を告げた専門家についての質問,③告知以降に関わった信頼できる専門家についての質問:②の一部と共通項目,④障害受容尺度:倉重・川間(1995)が作成した22項目,⑤コーピング尺度:尾関(1995)が作成した14項目,⑥自由記述:告知の際の要望,および調査に関する感想など。
【結果・考察】
障害受容尺度は「ネガティブ態度」「対社会的態度」「養育態度」「障害観」の4因子になり,因子別で比較したところ,父母間において「ネガティブ態度」では母親の得点が高く,「障害観」では父親の得点が高いという差が見られた(仮説①実証,下図参照)。しかし,専門家に対する評価の高低の間ではどの因子にも差は見られなかった(仮説③棄却)。コーピングと障害受容の関係については,「回避的対処」得点が高ければ,「ネガティブ態度」得点が低くなり,同時に「養育態度」得点は高くなる,という2つの関係が重回帰分析で明らかになった。しかし,父母間,夫婦間,専門家の評価の高低間においてそれぞれコーピングと障害受容の関係を比較したところ,一貫した傾向が見られなかったため,障害受容とコーピングの間に明確に関連があるとは言い難い(仮説④棄却)。専門家に対する評価は告知をした専門家のほうが,告知以降に関わった専門家よりも多くの項目で評価が低かった(仮説②実証)。それを裏付けるように,自由記述においては,告知した専門家に対する具体的な批判の方が多く挙げられていた。
尺度構成などで多くの問題点も提起されたが,専門家に望む親の声を直接聞くことが出来たのは,とても有益なことであった。
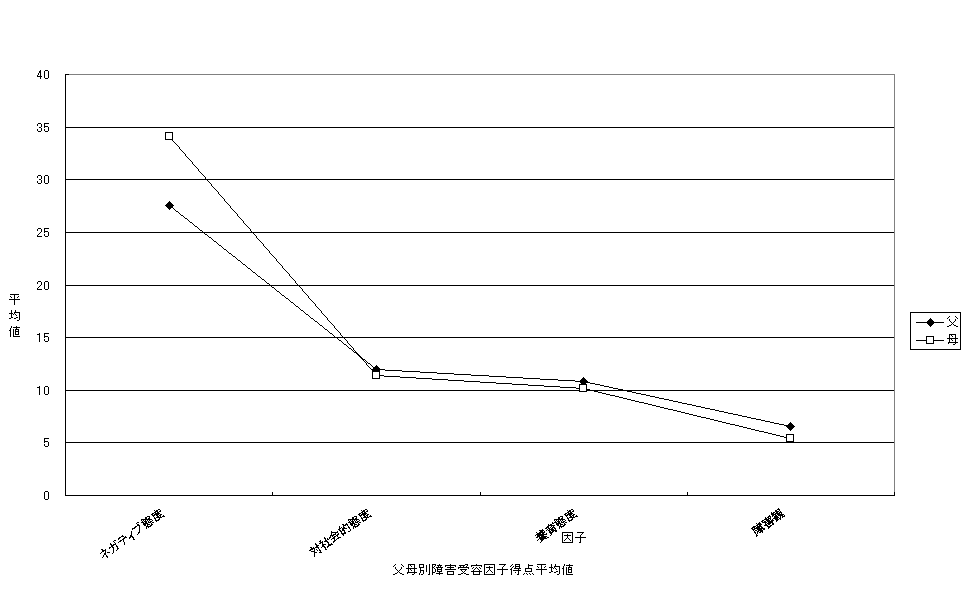
(指導教員 豊村和真 教授)