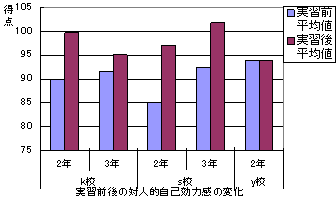[ 研 究 1 ]
【目的】
看護教育において重要な位置づけにある臨地実習では,看護の対象となる患者や,学生の学習を支える教員,指導者らとの対人コミュニケーションが実習の成果を左右するポイントとなる。そこで,Banduraの自己効力感概念に基づき,看護学生が,臨地実習で主体的に看護を展開していくために必要な対人的コミュニケーションを自分がどのくらいうまく行えると思うかについての主観的評価を測定することを目的とする「対人的自己効力感尺度」をあらたに作成し,信頼性・妥当性を検証した。
【方法】
札幌市内2病院の看護師から得た意見をもとに40の予備項目からなる質問紙を作成し,札幌市内3校の実習前看護専門学校生を対象に調査を行った。回答結果から,分布の偏りやIT相関を調べ最終的に29項目にしぼり,主成分分析行い,信頼性・妥当性を調べた。
【結果と考察】
本尺度は「ニーズの把握」「情報・意思の伝達と共有」「ニーズ充足に関わる対応」「問題解決への積極的対応」のコミュニケーションの基本的概念からなる4つの下位尺度29項目(逆転項目1)から構成され,自己効力感が高い時の行動特徴を含むような行動遂行場面を想定した質問内容からなる。
Cronbachα係数,スピアマン・ブラウンの公式より求めた信頼係数から,高い内的整合性を持ち,一般性自己効力感尺度,Kiss-18,自尊心尺度,患者との関わりにおける自己効力感尺度との併存的妥当性が確認された。安定性,因子構造,不安傾向との関連,予測的妥当性に関して課題が残された。
[ 研 究 2 ]
【目的】
①実習前後の対人的自己効力感と,一般性自己効力感を調べ実習がこれらの自己効力感に及ぼす影響を調べた。
②課題固有の自己効力感は,一般性自己効力感をもとに判断されるという観点から,対人的自己効力感と一般性自己効力感との関連を検討した。
③学年・学校間による自己効力感の相違と実習体験との関連を調べた。
④自己効力感の高低による,実習体験の違いについて検討した。
【方法】
研究Ⅰの被験者を対象に,作成した対人的自己効力感尺度と一般性自己効力感尺度(坂野ら1986)を使用し,実習前後でそれらを測定した。また,実習後に,自己効力感に影響する4つの情報源を下位概念とする実習体験尺度を追加し測定した。
【結果と考察】
実習後,対人的自己効力感は上昇しており,それには実習の肯定的体験が影響していると考えられた。2年生のほうが著しい上昇傾向にあり,実習進度に伴う課題の困難さが関係していると考えられた。また,学校間の比較で,実習経験のない学生は実習前の対人的自己効力感を高く評価しており,未体験により他の一般的事柄からの判断が課題固有の自己効力感の判断に影響(認知的誤り)していると推測された。
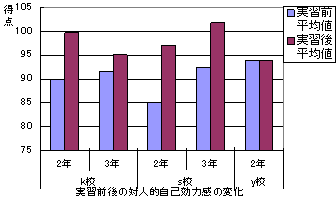
対人的自己効力感を高く維持できるものは,成功体験と情動的喚起の2つの情報源が効果的に作用し,自己効力感の上昇には代理的体験と言語的説得の2つが影響を及ぼしていた。逆に,自己効力感が低下したものはこれらの体験が少ないということになり,教師や,臨床指導者,看護師らの教示の仕方や,モデルとしてのあり方の看護学生の認知的側面への影響を示唆するものとなった。一般性自己効力感の高いものは対人的自己効力感を高く認知するが,実習により有意な上昇はなかった。本研究の看護学生の一般性自己効力感は高い傾向にあると推測されるが,実習が一般性自己効力感の変容にまで影響を与えることは難しいと考えられた。
(指導教員 豊村和真)