音楽の繰り返し聴取と快感情の関係
9907041
松尾 勉
問題意識
ある音楽を繰り返し聴くことでその音楽についての印象が変わることがある。例えば快感情を問題
にしたとき、なんども聴くにつれて快感情が高まっていく音楽もあれば、逆に減少していく音楽も
ある。このように音楽に対する快感情が変化するのは聴き手の何が変化するためなのだろうか?
一般には、聴く回数を増やすと快感情も高まることが言われている。
しかし実際にはすべての音楽が一様に繰り返し聴くことで快くなるわけではなく、なかなか快くな
らないものや、かえって快さが減少するものもある。それらのパターンを大別すると次の5つに分
けられる。
1 繰り返し聴取が少なくても快感情が高まるもの。
2 繰り返し聴取を多くしないと快感情が高まらないもの。
3 繰り返し聴取しても快感情に変化がないもの。
4 繰り返し聴取すると少ない回数で快感情が減少するもの。
5 繰り返し聴取してもしばらく快感情が持続し回数が増えることで徐々に減少するもの。
以上の五つである。
本研究はこうした繰り返し聴取の効果を検討するものである。
従来、刺激の繰り返し呈示が快感情に及ぼす影響を説明する際、最も重要な刺激特性として、刺激
の「不確定性(Uncertainty)」が挙げられてきた。
そこで本研究では不確定性として冗長性と典型性の2つのパターンを用意した。
目的
不確定性の操作として、ある和音系列に対して、リズムパターンの冗長性、ハーモニーの典型性の
2種類の操作を行うことによって、初期状態で、快感情がそれぞれの要因に対していかなる関係を
示すのかを、明らかにする。さらに、初期状態の快感情がその後の繰り返し聴取によってどのよう
に変化していくのか。また不確定性の高さの認知もどのように変化するのか。各要因ごとに検証する
方法
被験者
北星学園大学の大学生14名。
刺激材料
基本となる和音系列(RP0)に対し、RP0を最も冗長なものとし、リズムパターンの冗長性(を操作
した3系列(R1,R2,R3)を加え、4段階の冗長性を作成した。ハーモニーの典型性についても同様に、
RP0を最も典型的なものとし、典型性を操作した3系列(P1,P2,P3)を加え、4段階の典型性を作成した。
これらをそれぞれ9回ずつ聴取させて、それぞれの聴取後に快さと複雑さについて7段階評定させた。
結果と考察
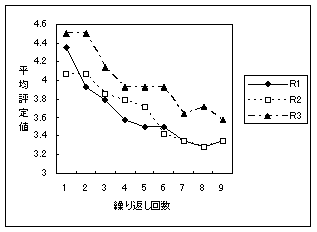 図1 R1.R2,R3の複雑さの推移
図1 R1.R2,R3の複雑さの推移
図1に示したとおり、冗長性の複雑さに関しては繰り返し聴取の影響により減少することがわかった。
しかし、快感情に関しては、残念ながら今回は有意な差が得られなかった。これは音楽経験により不
確定性に天井効果がでてしまったためと考えられる。
ここで面白いのは未経験者であればR1,R2,R3いずれの場合でも快感情が上昇しているが、経験者の
場合にはR1はある程度横ばいの後に減少、R2,R3に関しては横ばいのままとなっている点である。
もともと経験者のほうが未経験者に比べて不確定性が高いときには快感情が高いのだが、繰り返し
てもあまり影響を受けずに高水準を保っている。これは、ある程度不確定性が高いもの(冗長性が
低いもの)であればそれになれた後でも快感情が簡単には減少しないことをしめしているといえる。
また、典型性に関しては音楽経験の有無に関係なく快感情は横ばいのままであった。しかし、複雑さ
の評定に関しては減少していた。にもかかわらず快感情が変化していないのは音楽の構造上のルール
は強固で、それから逸脱したものはなかなか快いとは思えないのだろう。しかし、冗長性との結果を
あわせて考えるならば、もっとも冗長性の高いこのパターンの場合、繰り返し聴取とともに快感情が
減少しそうな気がする。今回は9回の繰り返し聴取だったがこの数を増やすことで変化が生まれるか
もしれない。
(指導教員 豊村 和真教授)
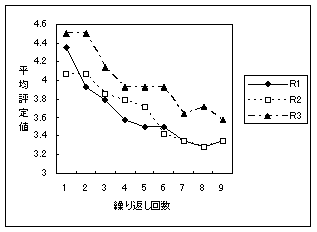 図1 R1.R2,R3の複雑さの推移
図1 R1.R2,R3の複雑さの推移