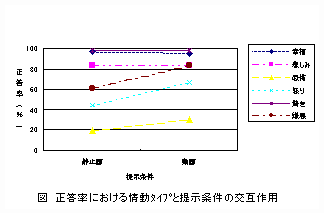
静止画と動画における表情認知に関する研究
9807075
山本 奈美
【目的】
日常生活において人が知覚している表情は,静止した表情ではなく,様々に変化する。心理学の分野において,表情から人がどのような心の状態を読み取っているのか,という表情認知に関する研究は,1970年代から精力的に行われてきた(Ekman & Friesen,1975 等)。しかし,こうした研究で用いられる典型的な実験パラダイムは,表情が明瞭に表れた写真を少数の情動タイプに分類する課題(強制選択課題)や情動尺度を用いた評定課題であった。1990年代に入ると画像処理技術の向上により,モーフィングという画像合成技術を用いて作られた人工合成顔画像を用いることによって,表情の動きを考慮した研究が行なわれるようになった(吉川,1997 等)。だが,動画と静止画における表情認知がどのように異なるかは検討されていない。また合成された画像を用いることは,厳密な心理学的分析にそぐわないともいえる。
本研究では,表情表出者に自然な表出を教示した表情動画を用い,静止画における認知との比較を行なうことで,動きの中における表情の役割を明らかにする。本研究の仮説は以下に示すとおりである。
仮説1:先行研究と同様に,特に幸福顔において,他の感情と比較し有意な正答率が得られるだろう。
仮説2:静止画実験では認知されにくい感情が,動画を用いることで正しく認知されるであろう。
仮説3:動画において静止画よりも強い感情強度を示すだろう。
【方法】
被験者:北星学園大学の学生40名(男性:15名,女性:25名)に実施した。顔の既知性効果を避けるため,表情表出者と面識のない者に限定した。
材料:8名の表情表出者(全て女性)に自然な表情表出を求め,撮影された動画から静止画を画像ソフトを用いて取り出し,それぞれの表情画像を作成した。表情以外の一切の要因を排除するために,撮影の際に収められた音声は全てカットした。なお,動画の長さは2秒間に統一した。さらに感情強度を統一するために,4人の観察者によってより強い表出であると感じる4名を選出した。
手続き:ノート型パソコン上において,PowerPointを用い,被験者へ表情画像の提示を行なった。最初に4人の表情表出者の「幸福」「悲しみ」「恐怖」「怒り」「驚き」「嫌悪」の6つの基本感情を表した静止画24枚をランダムに提示し,被験者に回答用紙にその情動の種類と感情強度を7段階で回答させた。その後動画24枚を提示し,同様に回答させた。
【結果と考察】
正答率を逆正弦変換した数値を用い,正答率に関して性別×提示条件×情動タイプの3要因分散分析を行なった結果,正答率に性差はみられず,提示条件×情動タイプに交互作用がみられた(図参照)。また多重比較の結果,情動タイプそのものの認知順は提示条件に大きく影響されず,肯定的情動である「驚き」「幸福」が他の情動に比べてより正確に認知されることが示された。これは先行研究と対応した結果であり,仮説1は証明されたといえる。対応のあるT検定で比較した結果,静止画を用いた先行研究においても認知されにくい「嫌悪」「怒り」「恐怖」は,動画において認知されやすいことがわかった。また全体の正答率も動画が有意に高かった。よって,仮説2は証明されたといえる。
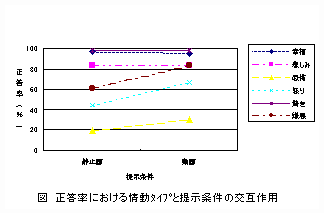
同様に感情強度に関して,性別×提示条件×情動タイプの3要因分散分析を行なった結果,感情強度に性差はみられず,提示条件×情動タイプに交互作用がみられた。また多重比較の結果から,単純に肯定的・否定的情動の順ではなく,正答率と対応していないことがわかった。「驚き」は提示条件に関わらず強い感情強度であり,対応のあるT検定においても動画において「幸福」は弱く感じられ,「悲しみ」「嫌悪」「怒り」といった否定的情動は,逆に強く感じられることが示された。よって,仮説3は一部証明されたといえる。
今後の課題として、被験者の認知様式といった要因に加え、実験条件として提示条件順や,表情刺激の質等も考慮する必要があるといえる。
(指導教員 豊村和真教授)