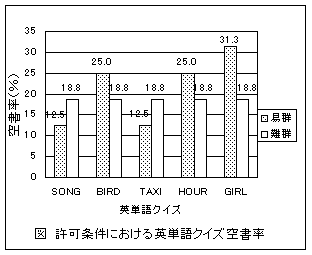【目的】
日常,我々は,なかなか思い出せない漢字の形態や単語の綴りなどを想起しようと試みる時,指で机や宙に文字をなぞることがある。この自発的な書字行動・動作は,言語学者,蓮實(1977)により初めて報告され,佐々木・渡辺(1983)により,「空書」行動と名づけられた。佐々木・渡辺(1983)は,空書行動が日本人成人にほぼ普遍的な行動として出現し,特定の思考課題の解決を強く促進する認知的な機能を持つことを示した。また,漢字圏及びアルファベット圏からの留学生と日本人学生に対し,英単語を用いた実験を行い,空書行動が漢字圏に固有であり,漢字圏の者は英単語においても空書を利用することを報告した。この結果は,漢字習得経験に起源をもつ,特殊な思考方略が他の言語習得事態へ転移していることを示唆した(佐々木・渡辺,1984)。
本研究では,漢字課題においては日本人成人にほぼ普遍的に出現し,解決を促進する認知機能を持つ空書行動が,英単語課題においても出現し,漢字と同様に認知機能を持つかを検証する。
【方法】
右手書字の日本人大学生32名を被験者とした。空書条件(許可,禁止)と課題条件(易しい,難しい)を設定し,許可易条件,許可難条件,禁止易条件,禁止難条件に各8名ずつ配置した。課題は漢字字形素統合課題(漢字クイズ〜(「糸」,「口」,「月」=「絹」)とアルファベット並び替え課題(英単語クイズ〜「S」,「O」,「N」,「G」=「SONG」)で,継時的に提示される漢字字形素やアルファベットから,それらが組み合わされて完成できるひとつの漢字,英単語を想起することであった。課題は各5題ずつであった。漢字クイズは,佐々木・渡辺(1983)が考案した「漢字字形素統合課題」と同様の課題を使用し,英単語クイズは高校入試レベルの英単語を使用した。村上(1991)を参考に,易条件の場合は字形素・アルファベットの刺激は筆順通り提示し,難条件の場合は順不同とした。刺激は全て3秒ずつ提示され,全ての刺激が提示し終わると,被験者は口頭で解答させられた。さらに被験者には,英語の学習方法や成績,好み,課題の難易度についてのアンケートに記入させた。
【結果・考察】
英単語クイズで空書を出現させた被験者は空書許可条件16名中,8名(50%)であった。これは漢字クイズの12名(75%)よりは低いものであった。これは課題の内容によるものと考えられる。漢字クイズでは字形素を組み合わせる課題であるのに対して,英単語クイズでは単にアルファベットを並べ替える課題であるからだ。課題の質は佐々木・渡辺(1983)でも使用した特殊な課題が空書を引き起こしたことが指摘されている(住吉,1996)。一語当たりの空書回数に関わらず,空書生起=1,生起せず=0とし,被験者の空書頻度を算出し,χ2検定を行ったが,有意な差はみられなかった。各問毎の空書頻度をみると,「SONG」,「TAXI」以外は易条件で難条件よりも空書が出現していることがわかる(図参照)。
英単語クイズ正答数については,条件を個人間要因とする1要因分散分析を行った結果,条件の主効果みられた(F(3,28)=7.69,p<.001)。TUKEY法による多重比較の結果,許可難・禁止難条件に比べて許可易・禁止易条件の正答数が有意に高かった。許可易条件,禁止易条件の英単語クイズ正答数の平均値はともに4.25,これに対し,許可難群の平均値は2.13,禁止難群は2.25であった。この点でも課題の内容に要因があると考えられる。しかし,易条件で空書が難条件よりも多くみられ,正答数も多いことは,空書が課題解決促進機能を持つことを示唆している。
空書の起源に関連して,漢字想起時に空書を生起させる被験者は,英単語想起時にも空書を生起させるのか,許可易条件,難条件において,漢字空書頻度と英単語空書頻度の差について,対応のあるt検定を行った結果,有意な差はみられなかった。差がみられなかったということは,漢字空書頻度と英単語空書頻度には差はなく,漢字空書と英単語空書には関連があることが示唆された。