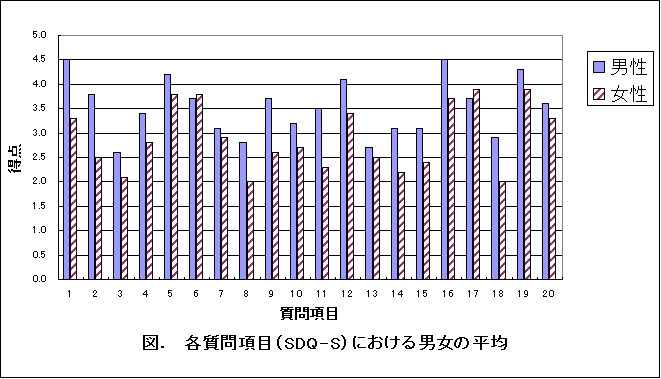方向感覚について−認知地図の視点から−
9807006
有馬 奈美
【目的】
竹内(1992)は,方位評定課題とSDQ-S(方向感覚質問紙簡易版(Sense of direction Questionnaire-Short Form):SDQ-S)との並存的妥当性を検討し,その下位尺度1が大規模空間と,下位尺度2が身近な空間との方向感覚に関係していると指摘した。本研究では方向感覚の自己評価としてSDQ-Sを用い,認知地図の歪みが道に迷う原因と考え,実際に持ち備えている方向感覚を認知地図の面から検討した。
JR総研は自己評価している方向感覚と実際に持ち備えている方向感覚とは一致しない,と示した。また,実際に持ち備えている方向感覚には性差がみられないものの自己評価する方向感覚には性差がみられた。以上の先行研究を踏まえて以下の目的をもとに,方向感覚について検討する。
1.自己評価している方向感覚と実際に持ち備えている方向感覚が一致しているかどうか。また,実際の方向感覚に性差はみられるか。
2. 方向感覚の自己評価に性差がみられるか。
3. SDQ-Sにおける2つの下位尺度により空間(身近・大規模)での方向感覚に違いがみられるか。
【方法】
被験者:大学生35名(男性17名,女性18名)
手続き:身近な空間として大学構内にある建物について思い出させ,あらかじめ書き込まれているランドマークの位置関係を基準に7地点の位置を書かせた。大規模空間として日本の都市・日本周辺の国の都市についての位置である7地点を,あらかじめ書き込まれている2地点の位置関係を基準に書かせた。以上2種類の課題に回答させ,最後に方向感覚質問紙(SDQ-S)に答えさせた。
【結果と考察】
※被験者の分類:SDQ-Sにおける自己評価を得点化し,被験者を2群(高群・低群)に分け,方向感覚意識レベルとした。
1.目的1の検討
目的1を検討するために,方向感覚意識レベル*性別の2要因分散分析を行なった。結果,自己評価している方向感覚と実際の方向感覚は必ずしも一致しないという結果が得られた。また,実際の方向感覚に性差はみられなかった。先行研究を支持する結果となった。
2.目的2の検討
方向感覚の自己評価に性差がみられるかを検討するため,平均の差の検定を行った。その結果,地図に関する項目・実際に行動する際の方角に関する項目・目印の記憶に関する項目で男性の方が有意に良い自己評価をしていた(図参照)。男性は,女性よりも地図を読み取ることが得意であり,実際に行動する際も方角を手がかりにしたり目印を記憶することに長けていると自己評価した。
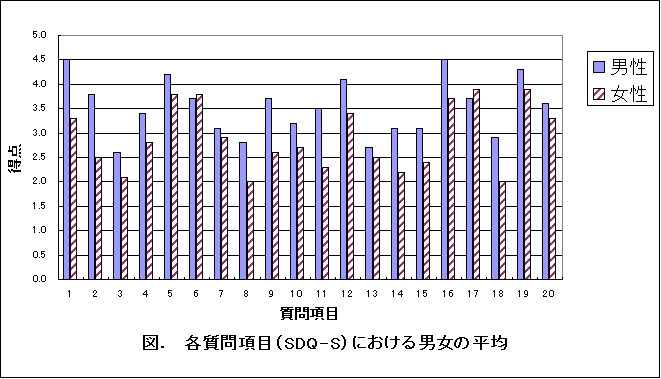
4. 目的3の検討
SDQ-Sにおける2つの尺度により2種類空間における方向感覚に違いがみられるかを検討するため,「認知地図の歪み」と尺度の相関係数を各空間でそれぞれ算出した。その結果,どちらの空間にも有意な相関関係はみられず,先行研究を支持しない結果となった。
以上の結果より,自己評価している方向感覚は実際の方向感覚とは一致しないこと,方向感覚についての性差は実際の方向感覚にはみられないが自己評価する際の方向感覚にはみられること,SDQ-Sにおける尺度は空間の広さと関係していないことが明らかとなった。
「女性のほうが方向感覚が悪い」という俗説に男性も女性も影響されているのではないか。女性にとってこの思いこみは,行動範囲を狭くしたり一人で出掛けることに抵抗を感じたりして,実際の方向感覚に影響することもあるのではないか。
本研究では取り扱わなかったが,土地や場所・建物への馴染み度がその空間における方向感覚に影響を与えていると考えられるため,馴染み度がどのように方向感覚に影響を及ぼしているのか,また,SDQ-Sにおける下位尺度が何に関係しているのか,という2つ点
が今後の課題となる。 (指導教員 豊村和真教授)