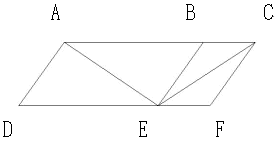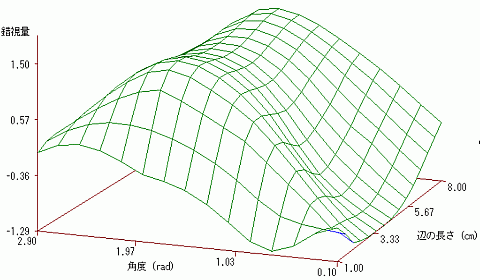サンダー図形における錯視の実験研究
9707048
野呂 千夏
[目的]
図1はサンダーの平行四辺形といわれ,左側の対角線AEと右側の対角線CEは物理的に等しい長さであるが,主観的には対角線AEの方は長く見え,対角線CEの方は短く見える。これを,サンダー錯視(Sander
illusion)という。
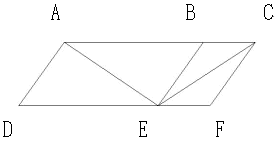
サンダー錯視の原因については様々な説明がなされているが, Rausch(1952)は「平行四辺形の短対角線は過大視され,長対角線は過小視される」事を発見し,この説に基づいてMetzger(1953)は「よき形態の法則」つまり,平行四辺形は良い形である長方形の歪んだ形であり,直立して良い形である長方形に近づこうとする傾向があるため,短対角線は過大視され長対角線は過小視されるとした。
浜口(1986)は以上の説に基づいて,対角線の長さと角度を固定し平行四辺形の上下の辺の長さを変えて実験を行い,平行四辺形の短対角線の過大視と長対角線の過小視,またより顕著な短対角線(長対角線)ではより過大視(過小視)されることを検証した。
本実験では,平行四辺形の上下の辺の長さと対角線の角度の2つの要因を変化させて検証し,対角線の角度および平行四辺形の上下の辺の長さが,対角線の長さに関する錯視にどのように影響しているのかを検討した。また,平行四辺形の対角線の錯視が「よき形態の法則」に従うのならば,正方形及び黄金律に近い長方形の対角線の錯視量は少なくなるのか検証した。
[方法]
正常な視力(矯正も含む)を持つ大学生20名を被験 者とし,EXCEL2000 VBA機能を使いパーソナルコンピュ ーター上で実験を行った。
刺激図形は,長さが7㎝,角 度が10度,30度,45度,60度,110度,150度,170度の対角線を持つ平行四辺形で,上下の辺の長さは1㎝,2㎝,4㎝,6㎝,8㎝で,7条件(角度)×5条件(辺の長さ)の35個の平行四辺形,各角度条件と同じ対角線を持つ長方形7個,統制条件としてそれぞれの対角線と同じ長さと方向を持った単一線分(斜線)7本,および7㎝の水平線1本の合計50図形とし,比較刺激である垂直線の長さを被験者調整法によって調整させた。
[結果と考察]
結果をスプライン補間しグラフ化したところ,滑らかな山型曲線(図2)となった。
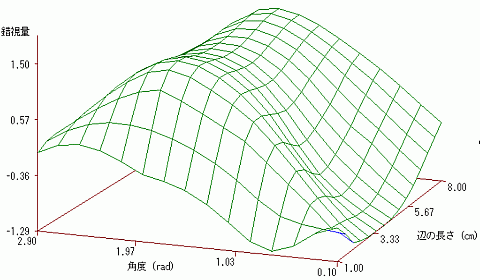
平行四辺形の対角線の角度を固定し辺の長さを変化させた時,より顕著な短対角線(長対角線)ほど過大視(過小視)が大きくなることは,部分的には検証できた。しかし,対角線の角度が大きな鈍角で辺の長さが長い図形では短対角線はより顕著になるが,過大視の程度は逆に減少した。これは,対角線の角度が大きな鈍角の場合だけであるのか,あるいは他の角度の時にも辺の長さが極端に長くなると同じ現象が起こるのか,今後の課題である。
平行四辺形の上下の辺の長さが同じで対角線の角度が違う図形においては,対角線は垂直に近い角度では過大視され水平に近くなるにつれて過小視されることから,水平・垂直線分の錯視の影響を強く受けていると考えられた。
長方形の中でも「良き形態」といえる黄金分割型の長方形や正方形だからといって,対角線の長さの錯視は小さくなるとはいえなかった。
(指導教員 豊村和真 教授)