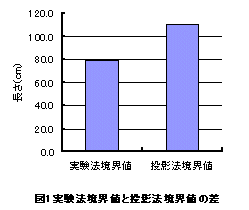

パーソナルスペースの方法論的考察
9707016
井上 未希子
[目的]
対人関係を展開する際,他者との間にとる最適な距離をパーソナルスペースという。パーソナルスペースの測定方法としては,実験室のような統制された状況で得られる相互作用距離の測定である実験法,被験者と他者を表す人物画やシルエットとの間の距離の測定である投影法などがあるが,それぞれの研究法の関連は明らかにされていない。そこで本研究はパーソナルスペースの研究方法である実験法と投影法の関連について,それぞれのストップディスタンス法による境界線の測定と,それぞれのマグニチュード推定法による心理的負荷感の判断値を用いて検討する。なお,本研究では情動指標として有用(大平,1991)とされる筋電図と,他者接近時の心理的負荷感の関連についても検討する。
[方法]
北星学園大学学生女性21名を被験者とし,実験法と投影法を行った。実験はすべて同一実験者により行われ,被験者とは初対面であった。なお,11名を実験法先行の群(ep群),10名を投影法先行の群(pe群)とした。実験室の床には,部屋の中央から角に向かって,50cm毎8ヶ所にテープを貼り,実験者はその間の6地点をランダムに移動し,その位置で感じる心理的負荷感を被験者に数字で答えさせ,同時に筋電図を用いて筋肉の緊張を測定した。また,実験者がゆっくりと被験者に近づき,被験者が心理的負荷感を感じ始めたところで実験者に制止をかけ,被験者と実験者の間の距離を測定した(実験法境界値)。実験中,実験者と被験者は視線を交差させた。なお,投影法に関しては,実験室の疑似模型を作り,それを挟んで実験者と被験者が向かい合って座った。実験者は実験者側の人形ををランダムに動かし,被験者は被験者側の人形を自分自身であるとみなしてその位置で感じる心理的負荷感を数字で答えさせた。また,実験者の人形をゆっくりと被験者側の人形に近づけ,被験者が人形の立場ならどの辺りで心理的負荷感を感じ始めるかを,実験者の人形の制止によって測定した(投影法境界値)。筋電図の測定部位は皺眉筋・眼輪筋・三角筋・大胸筋・外腹斜筋の5箇所であった。心理的負荷感の判断値については対数変換し,筋電図は平均波形化し地点ごとに「測定値」「最大値」を算出した。
[結果・考察]
投影法での境界線を実際の尺度に変換した数値は実験法での境界線よりも大きくなった(図1参照)。またpe群の方がその傾向が高かった(図2参照)。実験法のマグニチュード推定法による心理的負荷感の判断値については実験者との距離が縮まるほど緩やかに増加した。また,投影法でのマグニチュード推定法による心理的負荷感の判断値についても,実験者の人形からの距離が短くなるほど上昇した。実験法と投影法の方法による有意差は見られなかった。筋電図については,実験者との距離が近づくほど高くなる結果が得られたが,慣れや順序効果によるものもあるため,筋電図が心理的負荷感を測る生理指標として,必ずしも有用な方法であるとはいえないのではないか。投影法による投影法境界値は,実験法での実験法境界値よりも大きくなったため,渋谷(1985)の先行研究とほぼ同じ結果が得られた。しかし,心理的負荷感をはかる指標として用いられているマグニチュード推定法での結果は,実験法と投影法での有意差はみられなかった。したがって,パーソナルスペースの研究方法としての実験法と投影法とでは,得られる結果に違いがあることが示唆された。本研究では投影法で使用した装置の特性がパーソナルスペースの判断に影響を与えたことは否定できず,その関連性についての詳細な検討を行う必要があるだろう。
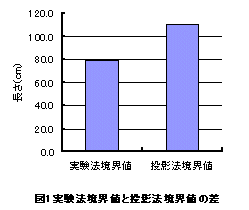

(指導教員 豊村和真教授)