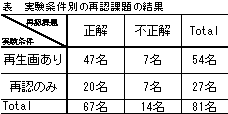晴眼者の触覚による図形認知と視覚による図形再認の研究
9707005
浜田 弓子
[目的]
Ikeda and Uchikawa(1978) および塩入・池田・内川(1983)では,プラスチック製のシートに描かれた凸線の刺激図形を目隠しの状態で触覚認知させた場合と,触覚認知後,紙に覚えているその図形のイメージを描かせその再生画を視覚により認知させた場合とでは<>刺激図形の認知に差が生まれると報告している。
中内(1999)は,被験者数を増やし,要因をつけくわえ実験をおこないIkeda and Uchikawa(1978)での現象は起こりうることを実証した。中内(1999)はその中で被験者に再生画を描かせた際,様々な再生画が得られたことから,分析するためのデータ化が困難であったとされた。そのため被験者本人の認知を知るには「再認課題」に方法を変更する必要があるとしている。本実験は,被験者の最終的な図形認知を理解するために触覚認知後,「再生課題」も導入しつつ,刺激図形を含む図形をいくつか提示し被験者に答えさせる「再認課題」で実験をすすめ,触覚と視覚のイメージ形成について検討する。
[方法]
被験者は皆晴眼者で女性19名男性8名の27名であった。中内(1999)でもちいられた刺激図形と要因のうち図形の大きさ(大・中・小),触覚認知にもちいる手(右・左・両),触覚認知の制限時間(2,4,8分)を割り付けた。再認課題で被験者に提示する図形を予備実験により刺激図形を含め7つとし,刺激図形ごとに6つずつ用意した。実験条件として,触覚認知課題後に再生課題をおこなう再生画あり条件とそれをおこなわない再認のみ条件と二群にわけ,「再生しそれを見ることで図形を認識できる」という現象の追実験をおこなう。また,再認のみ条件との間に差が見られるかどうかも検討する。方法は被験者にアイマスクをさせ刺激図形を触らせ回答を求める。刺激図形を触っている間,触っていて感じたことや思ったことはその都度報告するよう求めた。触覚認知課題後,触っていたものを描かせ何であるか再び回答を求める。その後,A4用紙に刺激図形を含むいくつかの図形を印刷したものを提示し被験者自身が触っていたと思うものの回答を求めた。再認のみ条件は再生画を描かせなかった。また,触覚認知以外で手や指を動かすことを制限した。 刺激図形は池田図形,望月図形,中内図形の三種ずつランダムに提示した。 再認課題で提示する図形の正解の位置もランダムにした。
[結果と考察]
全体の触覚認知課題の正解率は0.29,再認課題の正解率は0.82と有意に差が開いた。 再生画あり条件で触覚認知課題から再生課題への成績上昇は0.37から0.42であったが被験者数の少なさから有意な差は見られず再生画により図形の認知に至るという現象は本実験では見ることができなかった。再生画あり条件と再認課題でノンパラメトリック検定をおこなった結果T>χ2(1,
0.05)であった。しかし,再認のみ条件の被験者数が少なく信憑性にかけ両実験群に差があるとは言いきれない。
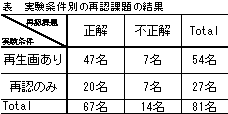
再認課題における反応時間の分散分析の結果,実験群の差はなかった。再認課題での成績に有意差が見られた(F(2, 78)=14.71 p<.001)。触覚認知課題の成績のうち正解と不正解に有意な差があった(F(2,78)=11.42
p<.001)。 どちらも正解ほど反応時間が短いという結果となった。触覚で得られた情報が明確なほど反応が早く,不明確なほど再認課題で時間をかけても不明確なものとなり不正解にいたるようだ。
また,再生課題では認知を成功させるものもいたが被験者によっては触覚認知課題で得られた情報をゆがめてしまう結果となった。やはりパーソナリティが関係する可能性もあるが,割り当てられた要因が影響することも考えられる。これについての検討は要因を一定にして行うことが必要だろう。本実験では実験条件別で有意差は見られずどちらの状況においてもパタン認識が正確になされており視覚イメージが優位に働いていることを示している。今後,被験者の触覚による図形認知を知るには再生画を描かせず再認課題へ完全に移行することも方法としてとることができるだろう。本実験での再認課題は提示図形に不備が多く新たな検討が必要である。
(指導教員 豊村 和真)