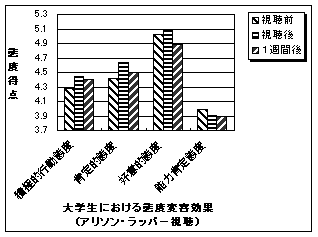【目的】
障害者に対する態度を受容的に変容させる方法として直接的接触ではなくても、障害をもつ人に関するビデオ等の視聴覚教材を視聴させる間接的接触が態度変容を生じることが確認されている。そこで、本研究では、大学生・専門学校生を対象にして、障害者を取り扱った映像の視聴前と視聴直後の態度変容効果を確認すると共に、1週間後の態度変容の持続性を確認することを目的とした。また、交流経験の有無によって態度変容効果があるか、内容の異なる2種類の映像を提示することで、障害者に対する態度変容にどのような影響をもたらすかを確認することをも目的とした。
【方法】
北星学園大学社会福祉学部の福祉心理学受講者(2~4年生)のうち映像の視聴前・視聴直後・視聴から1週間後の3回の調査・実験を全て出席した35名と、介護福祉系専門学校の(1~2年生)のうち視聴前・視聴直後の2回の調査・実験を全て出席した84名を対象とした。
①フェイスシート:回答者について、以前の障害児(者)との交流経験の有無、及び定期か不定期か、視聴直後において以前に今回の映像を見たことがあったかいなかの視聴経験の有無、②態度受容尺度:徳田(1990)が作成した尺度を元に、修正した25項目を回答させた。③実験に用いた映像:編集する際には、態度変容が受容的・非受容的に影響しやすい場面等を取り出した。一つは、両手両足がなくてもありのままの自分として受け入れ、様々な人と交流する活気に満ちた人生を送るシングルマザーの「アリソン・ラッパー」、もう一つは、両手両足がないという障害のために、過酷な人生を送ってきた「中村久子」の映像を各15分ほどに編集したもの。
【結果・考察】
態度受容尺度は「積極的行動態度」「肯定的態度」「好意的態度」「能力肯定態度」の4因子で構成された。「アリソン・ラッパー」の視聴直後には、「肯定的態度」「好意的態度」が受容的になり、全体的に各因子でも受容的な態度になる傾向がみられた。「好意的態度」のみ持続性がみられなかった(図参照)。多少の援助は必要とするものの、自分のできる限りの力で子育てをし、明るく積極的に行動するアリソンの生き方やパーソナリティを肯定的にとらえ、障害者自体を社会的に、または自分の領域に受け入れたいと考えたといえる。そして、積極的に障害者と交流したいと考える。しかし、「中村久子」の視聴では態度変容の差はみられなく、全体的に各因子で受容的態度が低くなっている傾向にある。また、男女別に比較したところ、男性よりも女性の方が受容的で、男性は視聴直後には非好意的態度となった。生活の困難から3回の結婚をしているが、そこで男性の観点から非好意的態度になった原因といえる。中村久子は母親に身売りされ、自尊心が崩壊しながらも懸命に生きていく壮絶な人生に、障害者と共に生きることに対する戸惑いやネガティブな態度が形成されたと考えられる。また、交流経験の有る人の方が無い人よりも態度は受容的で、交流経験の有る人の方が態度の持続性がみられた。交流経験の無い人は、その場限りで形成された態度であったために、持続性がみられないと考えられる。
本研究において、変容効果をもたらす映像の内容について、障害者が自分をありのままに受け入れて、そこから懸命に生きているという場面があれば、視聴者にとっても、素直に受け入れやすく、その感動が受容的な態度として置き換えられると考えられる。また、障害者がネガティブな性格よりも、ポジティブな性格の方が、態度が受容的になりやすく、好意的態度を形成しやすいという結果であった。 (指導教員 豊村教授)