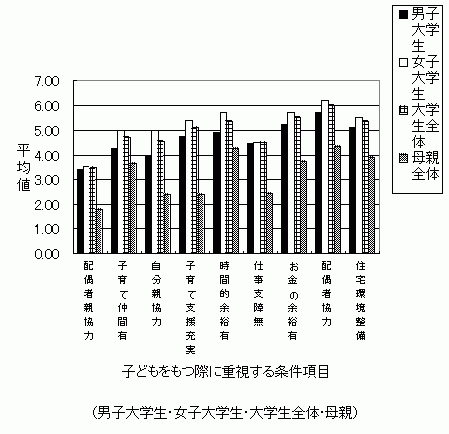大学生における子どもの価値について考察
0007014
井尾 友美
【目的】
子どもの価値とは何かということを改めて考えるために、ごく近い将来に子どもをもつ可能性が高い大学生が、子どもにどのような価値を求め、自分のライフコースの中に位置づけているのかについて検討する。
仮説:(1)大学生の子どもの価値は、母親を被験者とした先行研究とは違う形の因子構造をもつ、(2)大学生の子どもの価値は男子学生と女子学生とでは異なった因子構造をもつ、(3)子どもをもつ際に重視する項目(条件)は大学生男女では異なる。
【方法】
被験者:北星学園大学学生294人(男137人、女167人)、北星学園大学学生 (男15人、女39人)とその母親の対応54組
調査内容:フェイスシート、子どもの価値についての質問55項目、子どもをもつ際に重視する条件についての質問9項目をそれぞれ7段階評価で評定させた。子どもをもつ意識についての2項目については当てはまるものを選択させた。加えて、母親へは子どもの現在の人数についての質問項目、自由記述を設けた。
【結果・考察】
(1)<大学生全体の因子構造>〜第1因子:「自分のための価値」、第2因子:「条件依存」、第3因子:「精神的支え」、第4因子:「自己優先」
(2)<男子大学生の因子構造>〜第1因子:「自分のための価値」、第2因子:「条件依存」、第3因子:「期待と不安」、第4因子:「自己優先」。
<女子大学生の因子構造>〜第1因子:「自分のための価値」、第2因子:「条件依存」、第3因子:「子どもへの期待」、第4因子:「精神的支え」、第5因子:「自己優先」。
現在の社会状況下では、子どもの世話を直接的にする機会が多くなる可能性の高い女子大学生(将来の母親)において子ども、子育てに対して不安感や苦労感が現れていない反面、男子大学生(将来の父親)において、子育てへの不安感や苦労が意識されていることが今回の因子分析で明らかになった。また女子大学生は子どもが自分の支えになってくれることを子どもに見出している。大学生としての特徴は、「自己優先」因子である。この因子、項目は柏木・永久(1999)の先行研究ではなかったものである。「子どもをもつ親」としての意識よりも、「私」、「自分」という意識のほうが優先したい意識が表われている。
(3)大学生男女間での子どもをもつ際に重視する条件の差の検討を行ったところ、「子育て仲間がいること」、「自分の親が子育てを手伝ってくれること」、「子育て支援(保育所の充実等の公的な支援)が十分にあること」、「時間的に余裕があること」、「お金に余裕があること」、「配偶者が子育てを手伝ってくれること」、「子どもを育てる住宅環境が整っていること」においては、男子大学生よりも女子大学生でより重視されている。これは、子どもを直接的に育てる役割が女子大学生(将来の母親)に期待され、また女子大学生自身も子育てを担うという意識が強いためではないかと思われる。大学生男女問わずに母親世代よりも、子どもをもつ際の条件を重視している事から、今後は公的・私的な支援がより充実される事が望まれ、子どもを夫婦という家庭内だけでなく、社会全体で育てるような条件・環境整備が必要であり今後整備すべき課題である。
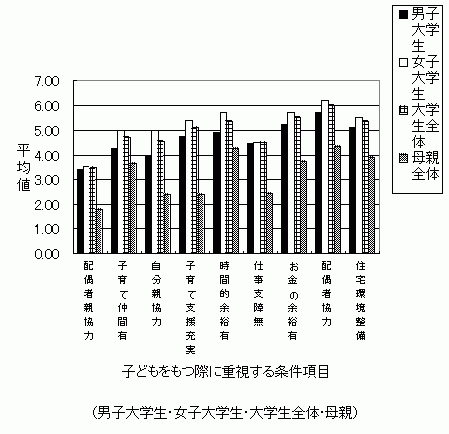
(指導教員 豊村和真 教授)