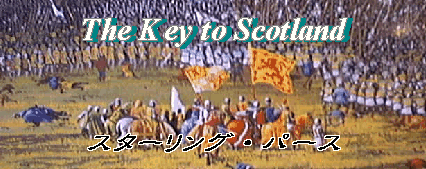
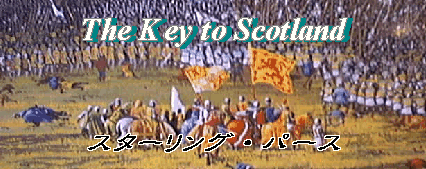
アバディーンから史跡めぐりの日帰り旅行に行くうち、歴史上有名な人物の名前を覚えるようになった。それはウィリアム・ウォレス(Sir William Wallace)であり、ロバート・ザ・ブルース(Robert the Bruce)であり、メアリー・クイーン・オブ・スコッツ(Mary Queen of Scots)であり、ロブ・ロイ(Rob Roy)である。そしてスコットランドに住んでいるからには、そういった人物にかかわる場所にも行ってみたいと思うようになった。それは、バノックバーン(Bannockburn)があるスターリング(Stirling)であり、スクーン宮殿(Scone Palace)があるパース(Perth)であった。
「スターリングまでは遠いなあ、アバディーンからは」
地図を見ながら、スターリング行きを長いこと躊躇していた。正確な距離はわからなかったが、地図上では片道130マイル(約208㎞)以上ありそうだった。かつてネス湖に行ったときにも片道130マイル程度走ったことがあるが、この時はどちらかといえばアバディーンよりも田舎に行く感覚であった。しかしスターリングはアバディーンよりは小さな町であるとはいっても、その先にはグラスゴー、エディンバラがあって、都会に向かって走るような気持ちになり、『大丈夫だろうか』との意識が強かった。
ところで、ウィリアム・ウォレス(1272-1305)は、映画『ブレイブ・ハート』でその生きざまが紹介されてさらに有名になった(ということを、恥ずかしながらアバディーンに来てから知った)。ウォレスは、イングランドの支配下にあった当時のスコットランドを独立させるためにイングランドと戦った英雄だ。その戦いは1297年、スターリング・ブリッジで展開され勝利、しかし翌年、フォルカークの戦いでエドワードⅠ世率いるイングランド軍に大敗して捕らえられ、ロンドンまで引き連れられてそこで惨殺されてしまったという。
ちなみに、スコットランドの国花はアザミ(thistle)。これはデンマークからスコットランドに侵入したバイキングが、裸足でアザミが咲いていた堀に入ったため、アザミの棘を踏んで侵攻ができなくなったという故事に由来するらしい。聞くところによれば、若きウィリアム・ウォレスの彼女がくれた花もアザミ。その彼女がイングランド軍兵士に殺されてしまったために、ウォレスは復讐のためにイングランド軍と戦ったのであるともいう(どちらも良くできた話だ)。
一方、ロバート・ザ・ブルース(1274-1329)は、ウォレスが惨殺されたあとの1306年、スクーン(Scone)でスコットランド王として戴冠する。ロバート・ザ・ブルースがスコットランド王になったときにもイングランド王はエドワードⅠ世。しかしエドワードⅠ世は1307年に死んでしまう。彼のあとを継いだのが息子のエドワードⅡ世。この息子は父親より軍事的な才能はなかったようだ。ロバート・ザ・ブルースは、ウィリアム・ウォレスのあとを引き継いでスコットランドの独立をかけてエドワードⅡ世率いるイングランド軍とスターリング郊外のバノックバーンで戦う。時に1314年のことであった。
ここで書いたことは、すべて当地に来てからの聞きかじり。13世紀後半から14世紀初頭といえば、マルコポーロがアジア周辺を徘徊していた時期だし、日本では鎌倉時代。元寇の襲来に手を焼いていた時代だ。
さてスターリング行。
5月の中旬、我々はバノックバーン目指して、朝8時にアバディーンを出た。この日は朝からいい天気。最高気温は17度の予報。ドライブに最高の日和だ。自宅からA90に入ってそのまま走る。A90はアバディーン市内は速度規制が行われているものの、アバディーンの郊外に出れば全線二車線なので最高時速は70マイル(mph:約112㎞/h)。そのままA90を南下すればスターリングに到着するが、我々はストーンヘイヴェン(Stonehaven)からA92に入った。いい天気なので海沿いを走ることにしたわけである。左手に太陽の光が反射してキラキラ光る海が続く。右手には今が盛りの菜の花畑。やがてモントロース(Montrose)を過ぎアーブロース(Arbroath)を過ぎる。途中、ミュィルドラム(Muirdrum)付近のパーキングで10分ほど休憩。アバディーンからはちょうど1時間半、64マイルほど走ったところだ。
この先は、ダンディ(Dundee)からA90に戻り、パースの入り口でA90から自動車専用道路(M90)に乗り、途中、7番出口を下りてA91を走り無事スターリング到着のハズだった。が、まず、ダンディで道を間違えてA90に入るのに手間取り、しかもパースでは、M90に乗りながら、スターリング方面と書かれた標識に誘われてすぐA9に下りてしまったため、仕方なくA9を走ってスターリングに入ることになった。スターリングに入るとすぐ、左手にウォレス・モニュメントが見えてくる。やや走ると今度は右手にスターリング城も見えてくる。そしてやっと最初の訪問地、バノックバーンに着いたのは、予定より30分以上遅い、11時30分だった。アバディーンからはちょうど140マイル(224㎞)。
まずは、バノックバーンに設置されたベンチで持参の昼食(もちろん、おにぎり!)。やや雲はあるものの日差しは強く、かなり暑く感じた。
昼食後、NTS(ナショナル・トラスト・フォー・スコットランド)が設置しているヘリテージ・センターに入って展示物を見学した(会員の我々は、もちろん無料)。そこには、ロバート・ザ・ブルースの生涯や彼にまつわるエピソードを紹介する展示物、バノックバーンの戦いの絵巻物(まさに絵巻物といった感じの絵。ちなみにこのページのタイトル画はその一部)、あるいはスコットランドとイングランドの戦いの歴史などを紹介する展示があった。
バノックバーンの戦いは1314年である。兵力は、スコットランド軍5,500に対してイングランド20,000。圧倒的なイングランド軍の兵力だったわけだ。戦争が始まったのは6月23日、そしてスコットランド軍が勝利をおさめたのは6月24日。23日の夜、イングランド軍は、何を考えたのかバノックバーン付近を流れる川の近くの湿地で野営したという。一方スコットランド軍は丘の上で野営。24日には、スコットランド軍の攻撃に、湿地に足を取られたイングランド軍は為す術がなかったらしい(アザミの故事に似ているなあ。スコットランドは時々「足下の運」に恵まれるようだ)。
センター内には、近所の小学生が書いた絵も展示されていたが、スコットランドの小学校では1314年6月24日は特別な日として教えているのかも知れない(小生も忘れないだろう、個人的な理由で)。
 Robert the Bruce at Bannockburn |
印象に残ったのは、バノックバーンの戦いの絵巻物、ロバート・ザ・ブルースがかぶった兜、そして英国国旗のデザインを紹介したものなどだ。
バノックバーンの戦いの絵巻物は、ちょうど関ヶ原の合戦を連想させるような感じで、ロバート・ザ・ブルース率いるスコットランド軍(旗印は黄色地に赤のスタンディング・ライオン)とイングランド軍(こちらの旗印は赤地に黄色の横たわる3頭のライオン[たぶんライオン])。今でも、サッカーなどのスポーツ大会ではこのスタンディング・ライオンが描かれた旗が使われているし、セント・アンドリュース旗(スコットランド国旗)とともに、お土産屋などではスタンディング・ライオン旗が売られているので馴染みがある旗だが、ロバート・ザ・ブルースの時代には使われていたというから驚きだ。
兜は、誰でもかぶることができる、つまり体験することができるように展示されていたので、小生もかぶってみたが、これは相当重い。長い時間かぶっていたら首の骨が折れるのではないだろうかと思えるような兜だ。日本の武者兜とは違いきらびやかな飾りはなく、頭から首のあたりまでスッポリと覆う鉄の鎖でできた兜だ。これなら、相手に斬りかかられても持ちこたえることができそうだ(それにしても重い)。
また、スコットランドとイングランドが連合を組んだ1707年に、スコットランドのセント・アンドリュース旗とイングランドのセント・ジョージ旗を組み合わせて国旗を作ろうとしたらしい。そのデザインを巡っていくつかの案が考えられたようで、その時のいくつかのデザインが展示されていた。当初は、セント・アンドリュース旗が強調されたデザインの国旗が使われていたようで興味深い(イングランドの懐柔策の一つだったりして)。英国国旗が現在のようなユニオン・フラッグ(ユニオン・ジャック)になったのはアイルランドが連合王国に入った1801年以降だ。それによってセント・アンドリュース旗(スコットランド)とセント・ジョージ旗(イングランド)、セント・パトリック旗(アイルランド)を組み合わせた英国国旗ができたというわけだ(1949年にはアイルランドは独立してしまう。現在は北アイルランドとしてアイルランドの一部が英国に属している。ユニオン・フラッグをよーく見ると、左右上下が非対象なんですね)。
ヘリテージ・センターの展示物を一通り見た我々は、ロバート・ザ・ブルースの騎馬像に向かう。バノックバーンは地名であり、近くを川が流れる、なだらかな丘陵地帯である。そこからはっきりとスターリング城を望むことができる。ヘリテージ・センターから騎馬像までは徒歩でほんの5分程度。その騎馬像を見た我々はただただ無言。
『こんな風にしてここに立っていたんだろうなあ』(状況は違うが、思わず、仙台の伊達政宗の騎馬像を思い出した。)
その騎馬像の前には、ロバート・ザ・ブルースがバノックバーンの戦いでそのあたりに陣地を構えたという地点を示すサークル状の塀(へい)が設置されていた。そしてその塀の中に、1320年、アーブロースの修道院でロバート・ザ・ブルースを中心とする諸侯がスコットランドの独立を宣言した、いわゆる「アーブロース宣言」の一節となった文章を刻んだ石碑が建っていた。その石碑には次のような文字が刻まれていた。
「我々が戦うのは、栄光のためでもない、富のためでもない、名誉のためでもない、まさに自由のためである。」
これを読んで思わず出た言葉、「カッコイイねえ。」
バノックバーンを1時前に出た我々は、スターリング市街に入り、スターリング城を目指す。バノックバーンからスターリング城まではわずかに2.7マイル、10分程度である。スターリング城に入る道は、一方通行の石畳の坂道。登城する、といった雰囲気にふさわしい。駐車場入り口で駐車料金(£2)を支払う。駐車場には結構な数の車が停まっていたし、観光バスも停まっていた。
駐車場に車を停めてお城のゲートに向かう。ここはHS(ヒストリック・スコットランド)の管轄。我々は会員証を提示して内部に入る。最初に見たところは、かつてはボーリング場(日本で見るいわゆるテンピン・ボウルとは違う)だったという庭園。花が今が盛りとばかりに咲き、その奥の城壁の彫刻も見事だった。そこから城下を見れば、眼下に王室公園と庭園が、さらに遠くの町並みまで見渡すことができた。ここは、エディンバラ城と同じように岩城であり、エディンバラ城ほど大きくはないものの、雰囲気はエディンバラ城そっくりだ。
 |
その立地条件から、スコットランドとイングランドとの攻防の歴史がこのお城にはある。バノックバーンの戦いの時には、イングランド軍がスターリング城を占拠しており、ここからエドワードⅡ世が出陣している。さらにいえば、イングランドから見れば、スターリング城を手に入れることが、すなわちスコットランドを手に入れることと同じ意味を持つものとして捉えていたようで、スターリング城を落とすこと、それが「スコットランドへの鍵(Key
to Scotland)」だったわけだ。
我々は、まずお城の外壁の沿って四方を見てまわった。いずれの方向も遠くまで見渡すことができる。このお城から、我々が次に訪れようとしているウォレス・モニュメントもはっきり見える。
とはいえ、お城の内部は、いたって素っ気ない。むしろ、グレート・キッチンに代表されるようなかつての様子を再現した部屋や、グレート・ホールのような建物それ自体を再現したものが多いといった印象だ。
エディンバラ城もそうだが、これだけ広いともはやお城といった印象からはほど遠く、その立地条件と相まって、要塞以外の何ものでもないと思えてくる(実際、要塞として重要な場所として位置付けられてきたのであるが)。
 スターリング城からウォレス・モニュメントを望む |
スターリング城を出たのは2時30分だった。また石畳の道を下りることになるが、上りが一方通行だったから下りも一方通行。その途中に、アーガイルの宿(Argyll's
Lodging)がある。これは17世紀のルネッサンス様式の建物だというが、我々にはあまり興味がないのでこれはパス。やがて市街に入る付近で、上ってきた道と同じ道に合流してもとの場所に戻ることになる。
そこからウォレス・モニュメントを目指す。方向がわかっているので適当に走る。スターリングの街中にはライラックが咲いていて、しばし札幌を思い出す。約4.2マイル、12分ほど走ってウォレス・モニュメントの駐車場に到着。
 The National Wallace Monument |
ウォレス・モニュメントは遠くからも見ることができる小高い山の上に建っている塔である。その場所には、とくにはいわれはないようだが、ウォレスの功績を記念して建てたものらしい。
すぐに塔に通じる山道を歩けるのかと思ったら、何と、売店があり、その売店を経由して(ということはそこで入場料を支払って)山道に入るようになっていた。入場料(大人£3.30×2)を支払って売店の裏のドアを開けると、そこから山道が始まっていた。何気なく振り返ると、その方向にはゲートらしきものはなく入場料など支払わなくても山道に入ることができたのであった。
 なかなか凝っているモニュメントの彫刻 |
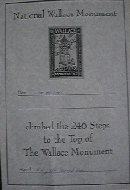 246段を登ったという証明書 (ネス湖でも同じようなものを買った) |
『なーんだ、ここから入ればタダだったじゃないのか?』
そんなことを思いながら割と急な山道を登る。途中で小型のバスが我々を追い抜いていった。そうなのだ、登れない人のために、別料金でシャトル・バスを運行しているのであった。
山道の途中まで来ると、今度は階段が続く。段差が不揃いの階段をエッチラホッチラ登る。その数170段(とはいえ、数えた者すべての数が違っていたのでだいたい170段といったところ)。階段の先にはウォレス・モニュメントがそびえ立っていた。
このウォレス・モニュメントのベースから見る風景も見事なものだったが、さらにモニュメント内部には階段があり、トップまで上ることができるようになっている。モニュメントの入り口にまた料金支払いディスクがある。
『ここでもまた料金がかかるのか? ひでぇ話だ』
と思ったが、下の売店で料金を支払わなかった者がここで支払うことになるというもので、我々がレシートを示すと、そこにスタンプを押してくれた(結局、下かここで料金を支払うシステム。だからこっそり山登りをしてもダメだというワケだ)。
モニュメントのトップには、幅の狭い、急な螺旋階段を上がらなければならない。階段の数は246段。途中3ヶ所に展示フロアがある。仕掛けのあるビデオ・シアターは面白かったが、それ以外は大したものはない。むしろここは、一気に上ることができない者(小生もその一人)のための休憩場所だ。
それでも子供達に誘われてがんばってトップまで上りつめる。小生にとっては苦手な場所だ(恥ずかしながらちょっとだけ高所恐怖症・・・)。見晴らしは、当然のことながら最高(裏腹に『早く下りたーい』)。
5分程度いただろうか、さっさと階段を下る。下ってみると意外と早くベースに下りてくることができた。考えてみれば、山道はシャトル・バスを利用することができるが、モニュメント内部は自分の足で上らなければならないので、駐車場からバスを利用するという人は、端から上らない方がいいかもしれない。
いい天気と山登り、プラスモニュメント上りのため汗がにじみ出てくる。スコットランドで汗をかいたなんて初めてだ。時計を見ると午後4時。もう一ヶ所行きたい場所があったが(パース近郊のスクーン宮殿)、この時間に移動しても到着時には閉館しているだろうと思い、アバディーンに帰ることにした。
帰りは、A9を走り、パースの手前でちょっとだけM90に乗り、パースからそのままA90をひた走った。自動車専用道路とはいっても、日本とは違って通行料金はかからない。そして片側2車線のA道路と変わらず最高時速は70マイル。A道路と違うのは、まさに自動車しか通行できないという点だけ。
パースからA90を70マイルで走る。フロントガラスに小さな虫がぶつかって来る。お陰でフロントガラスはワイパーを使っても汚れがとれない(道央自動車道でも同じ経験をしたことがある)。太陽はまだまだ高い。しかし太陽を背にして走るのでまぶしさはない。順調に走り抜けた我が愛車ローバーのお陰で、午後6時20分に帰宅することができた。この日の走行距離は273.6マイル(約438㎞)。行きはバノックバーンまで3時間30分、帰りは2時間20分。
『結構近いもんだなあ』
これは帰宅後の実感である。
翌日、再び同じ方向に走ることになった。
帰宅して、夕食をとりながら、スターリング城で見つけた最新の『スコットランドへようこそ2000-2001』(日本語版)を見ていると、パースにハイランド・クー(Highland
Coo)という当地の愛嬌のある牛などを間近で見ることができるという、パース・マート・ビジター・センター(Perth
Mart Visitor Centre)があると紹介されていた。かみさんがぜひ行ってみたいという。パースといえば、スクーン宮殿(Scone
Palace:ちなみにスコットランドのお茶うけ、スコーンと同じスペル。でも発音が違う)があるところだ。この2ヶ所を訪れるためだけに2日連続の遠出と相成ったわけである。
朝9時に自宅を出発。曇り空。途中でサンドウィッチを調達。そのままA90を走る。昨日と同じ道。時速70マイル。快調。しかし、アバディーンの郊外からストーンヘイヴェンの先まで、海霧で真っ白。ライトを点灯しなければならない状態だった。
『いい天気はそんなに続かないもんだ』
と諦めてはいたが、そんな霧のお陰で、右手に見えるハズの菜の花畑が霧の中にあり、しかも太陽の光がその上から射し込んでいるようで、ぼやっとした、何とも幻想的な風景を見ることができた。
幸いにして霧は海岸付近だけで、A90が内陸部に入ると青空が戻ってきた。普通ならば、パースまでA90を走れば早いのだろうが、ここでも違う道を走りたいと思い、フォーファー(Forfar)の先からA94に乗り換える。
A94は途中、いくつかの小さな町を抜けて走る道だが、街道筋に背の高い並木があり、これはこれでカントリーロードを走っているという実感が湧く風景だ。
A94を順調に走り、パースの手前のスクーンに入る。ここからA93に乗り換えてちょっといけば目指すスクーン宮殿に到着するはずだったが、どこでどう間違ったのかわからないが、いっこうにA93の標識が見えない。
『また昨日と同じだ』
A9を走ってUターンしたり、パースの街に入ってUターンしながら、やっとのことでA93に入ることができた。A93に入るとほどなくして左手にスクーン宮殿に通じるエントランスが見えてきた。
エントランスを入り、長ーく続く一本道を走ると前方に宮殿が見えてくる。その手前に料金所があり、我々の車が近づくと、女性が道路端に出てきて我々を待ち受けていた。その女性は、車の中を一瞥して「ファミリー・チケットにしますか」という。「お願いします」と小生。ここで£17.00を支払う。ファミリーで£17.00は結構なお値段(£1=¥180で¥3,060)。その料金所からすぐのところに駐車場があるので、その駐車場に車を停めるやいなや、子供達の声「なに、アレ!」
知らなかったが、ここはクジャク(Peacock)が住む宮殿だったのである。
 美しさを誇示する季節 |
時計を見ると、11時35分。アバディーンからは104.1マイル。まずは昼食ということで、駐車場の脇に設置されたベンチで、クジャクを見ながら昼食をとろうと移動した。ベンチに腰をおろしてサンドウィッチを食べ始めると、一羽の雌のクジャクが近づいて来た。どうやら食べ物をおねだりしているらしい。初めは気にしないで食べていたが、彼女がどんどん近づいて来て、我々にピッタリ寄り添うような距離に来たとき、「ちょっと恐いよ」と子供達。やはりあの目でじっと見られると、サンドウィッチも喉を通らない。食べかけのサンドウィッチを持って自動車に逆戻り。
あちらこちらから、クジャクの鳴き声が聞こえてくる。あの見事な羽を広げているものもいる。人間が近づいてもまったく気にしない様子。
 Scone Palace |
昼食後、宮殿内部へ。入り口で、日本語のガイドブックを購入(£3)。何組かの見学客が三々五々見ていたが、その中に、3人の日本人がいた。見るからに日本人だ。近づいたら声を掛けようと思っていたが、結局波長が合わず声を掛けることはできなかった。またこの宮殿は、NTSの施設とは違って写真撮影OK。小生は撮らなかったが(ガイドブックで十分)、一所懸命シャッターを切っている見学客がいた(日本人ではない)。
このスクーン宮殿。ここを見ずしてスコットランドを語るなかれといわれている。何故か。それは、歴代のスコットランド王がここで戴冠してきたから。もっと象徴的には、戴冠式で王が腰掛けた「運命の石(あるいはスクーンの石)」(Stone
of Destiny)があったから。
「運命の石」は、1296年に、かのエドワードⅠ世によってイングランドに持ち去られたという。今度は、イングランド王がウェストミンスター寺院で戴冠する時、特別な椅子の下に置かれたという。何故か。それはその石を椅子の下に置くことによって、イングランドがスコットランドを押さえるという象徴として使ったからである(ロバート・ザ・ブルースは1306年に戴冠したが、その時には「運命の石」はなかったわけだ)。
 The Stone of Destiny(これはレプリカ) |
その「運命の石」は1996年、700年ぶりにスコットランドに返還された。しかしその場所はスクーン宮殿ではなくエディンバラ城であった(チャールズ皇太子が即位するときはまたロンドンに持っていくという)。
我々も2度目にエディンバラ城に行ったとき、2月ということもあって我々以外の見物客がいない中、じっくり本物の「運命の石」を見てきたが、何のことはない、サンド・ストーン(砂岩)でできた小さな石である(その部屋の係員からゆっくり由来も聞いた)。現在、スクーン城にはその複製が置かれている。
また、この宮殿には、1976年6月19日から21日まで平成天皇が、1991年9月22日には皇太子が訪れ、記念植樹もしている(その時のスコップも展示してあるが、肝心の植樹した木を見落としてしまった)。
この宮殿、現在でもマンスフィールド伯爵家(現在の当主は第8代ウィリアム・デイヴィッド)が住んでいるため、内部は半分程度が公開されているに過ぎない。しかし、部屋数は40を超えるほどの建物で、宮殿とはいっているがお城といってもおかしくない(いろいろ見てくると、宮殿は住宅で、戦争に備えたものではないというのはわかるが、それ以外のお城との区分がどこにあるのか、わからなくなってきている)。
そんな宮殿なので、調度品、壁に掛かっている絵画などはお宝ばかり(これも不思議なことに、そんなお宝ばかり見てくると、そんなに感動もしなくなる)。
グルッと一回りして駐車場に戻ると1時35分。我々はクジャクに別れを告げて、次の訪問地パース・マート・ビジター・センターに向けて出発した。
しかし、ここで問題が一つあった。『スコットランドへようこそ2000-2001』にはパース・マート・ビジター・センターの正確な場所が記載されていなかったのである。簡単な地図にその位置を示すマークはあったが、それはA85とA9が交わる辺りに付いており、それ以外情報はなし。電話番号は記載されていたが、自分が今いる場所さえ説明できないので電話で問い合わせることなどできるはずがない。
『とにかくA85とA9が交わるところを走っていれば道標ぐらいあるだろう』
とアバウトに考えて探し回ったのがいけなかった。最初はA9に乗ってしまい、どんどんパースから遠ざかってしまう。慌てて引き返してパース市内に入ると、今度はどこでどう間違ったのか、A90に乗ってしまい、またまたパースから遠ざかる。A90から引き返し、パースに入ると、今度はあれほど探し回ったA93に入ってスクーン宮殿に逆戻り。
「もうだめだ。もう一回、A85付近を探して見つからなければ帰ろう」
何とかA85に入って直進。いくつかのランダバウトを越える。
『見つからないなあ』
と思った矢先、左手に、パース・マート・ビジター・センターの大きな看板が見えてきた。「あった、あった」(良かったー)
一時間程度探し回って、到着は2時50分。
 やっと見つけたマート・ビジター・センター |
 これがハイランド・クー |
ここは、牛や羊たちの取引所(mart)でそこがお土産屋、レストランなどの商店を経営しているような施設だった。早速お土産屋に入り、その奥にある見学施設に行った。大きな牛舎に何頭ものハイランド牛がいた。しかし、『スコットランドへようこそ2000-2001』に記載されていたようなイメージではなく、何となく肩すかし。楽しみにしていたかみさんもちょっと残念そう。
「ま、それでもハイランド・クーを間近で見られたのだから良しとしよう。」
というわけで、3時25分には車に戻り、A90に乗り換えて、アバディーン目指した。この日の走行距離は232.3マイル(約372㎞)。
スターリング、パースへの小旅行は、結局2日間にわたり、総走行距離は505.9マイル(約810㎞)だった。2日目の夜は、泥のように眠ったのはいうまでもない。
【ご紹介】
このページをアップしたあと、スターリングに住む優さんという方から、小生の知識不足からくる文章の誤りや歴史的事実についてスターリングそしてスコットランドの歴史についてコメントを頂戴しました(ちなみに優さんはスコットランド史の専門家)。
そのコメントを以下に紹介します。
| 1.ウィリアム・ウォレスについて フォルカークの戦いはスターリング・ブリッジの翌年の1298年、ウォレスの死はかなりあとですね。というのは、ウォレスは確かにこの戦いで負けますが、つかまってはいません。スコットランドの指揮権をロバート・ブルースに譲り、その後は当時スコットランドの同盟国だったフランスから援軍をつのろうとフランスに行ったとか、ローマ法王に嘆願に出かけたいう話があります。フランスからは結局協力は得られず、しびれを切らしてスコットランドに戻ったところで、同邦人に裏切られて(映画ではブルースが裏切ったような話になっていましたが、別の人です)捕らえれたのです。 「ブレイブ・ハート」はウォレスの名を国際的に広め、スコットランドの観光にも大いに貢献し、しかも観て面白い映画だったということでは評価できるのですが、あまり史実にこだわらないストーリー展開に、スコットランド史を勉強した人間は皆「!??」という感じでした。 なお、映画ではウォレスがハイランダー風に描かれていましたが、実際のウォレスはスコットランド南西部の地主の次男でした。ウォレスについてのくわしい話は、ナイジャル・トランターの小説をぜひ読んでみてください(英語ですが)。史料調査の丹念さでは定評のあるトランターですので、こちらは史実の歪曲の心配をせずに読めます。 2.ウォレス・モニュメントの場所について 場所のいわれはというと、スターリング・ブリッジの戦いの前夜から朝にかけて、ウォレスの軍はこの山のてっぺんに陣地を張っていたのです。小高いのでスターリング城から出てくるイングランド軍の動きがよく見える、というわけです。モニュメントの説明ではウォレスは全軍をここに置いて、イングランド軍が動き出すやいなや山をだーっと駆け下りて攻撃し、その猛攻の恐ろしさに度肝を抜かれたイングランド軍はパニックに陥った・・・となっていますが、私はこの説は嘘くさいと思っています。だってあの山から橋に向かって駆け下りられるわけがないじゃないですか。橋に面している側は絶壁です。回り道して裏側のあのだらだらの坂道を駆け下りて、さらにあの長い道を橋まで走らなくちゃならない。全然迫力出ないですよね。橋に着く頃にはくたくたです。と思っていたら、トランターの小説では実は山のてっぺんは見張りだけで、兵士は湿地に潜み、イングランド軍が橋を渡ろうとしたところに奇襲をかけたことにしていました。 3.運命の石について この返還された運命の石はにせものだといううわさがずいぶんあります。1950年にこの石を盗んだ連中が複製と交換したとか、いや、最初からイングランドはにせものをつかまされ、そうとは知らずにただの岩を後生大事にウェストミンスターに置いていたのだとか・・・。19世紀にパースの山中で大事そうに隠された石が発見され(これは砂岩でなく、白くて彫刻があったとか)、研究者が調査のため運び出したがその後行方知れずになったなんて話もあるし、いや、本物はロバート・ブルースの遺言によりハイランドのマクドナルド族に受け継がれたのだなんて話もあります。ミステリーなんですねー。 |
なお、優さんのホームページは、http://come.to/koiwaでご覧いただけます。
ここに優さんのご厚意に感謝します。